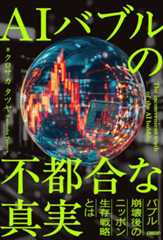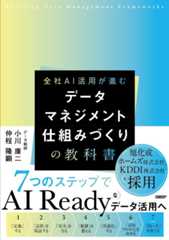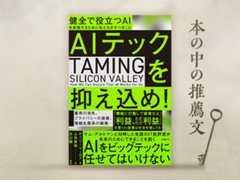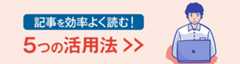グリコもユニ・チャームも苦渋、トラブル相次ぐERP導入に潜む大きな理解不足
ERP(統合基幹業務システム)の導入に失敗した挙げ句、ビジネスが止まる――。ERPにまつわるシステム障害が相次ぎ発生している。江崎グリコは独SAPのERP「S/4HANA」を使って構築した基幹系システムの障害で、プッチンプリンなどチルド品の出荷停止に追い込まれた。ユニ・チャームもS/4HANAと物流システムの連係を巡る障害で、製品の出荷に遅延が生じた。
なぜERPの導入はうまくいかないのだろうか。イチからシステムを構築するわけではなく、形のあるパッケージソフトを導入するにもかかわらず、だ。
SAPや米Oracle(オラクル)など大企業向けのERPパッケージを中心に、導入に失敗することは今に始まった話ではない。日経コンピュータのコラム「動かないコンピュータ」では2000年代前半から繰り返し、ERP導入の失敗事例を取り上げてきた。中には訴訟に至った事例もある。
筆者自身、これまでERP導入の失敗事例を取材する機会が複数回あった。ERP導入を巡った裁判の記録を閲覧したこともある。様々な取材を通じて思い至ったのは、関係者による「ERPに対する誤解」が導入失敗の最大の原因ではないかということだ。以下では大企業・中堅企業向けを前提に、ERP導入失敗の原因を考えてみた。
現場の生産性を犠牲にしても、経営を最適化するのがERP
ERP導入を巡る最大の誤解は、「パッケージソフトの合わない部分は、アドオン(追加開発)ソフトを開発し、自社の業務に合わせればいい」という考えを多くの人が持っている点だ。
ERPは経営の最適化を目的としたソフトウエアである。極端な話、現場の生産性が多少落ちたとしてもERPの持つ標準的な業務プロセスに合わせることで、企業固有の無駄な業務を削減し、経営判断に役立つデータを集めようというのがERPの基本的な思想だ。
そもそもエンドユーザーの業務を効率化するためのソフトウエアではないのだ。そのため、「合わない部分」は発生しない。「合わせる」のが当たり前だからだ。「ERPを導入した結果、実際にERPにデータを入力する経理担当者の業務負担が増した」と言って、導入を推進しているIT部門と現場部門がもめるケースはよくあるが、ERPの持つ業務プロセスや業務処理方法に合わせるのだから、負担が増すこともあるだろう。
そのため「合わない部分はソフトウエアを修整して合わせる」というのは本末転倒だ。世界中の企業の標準的な業務プロセスを提供しているERPパッケージの目的を損ねてしまう。
無理やり自社の業務に合わせるために、アドオンソフトやカスタマイズをした結果、ERPが標準で持つ業務プロセスやデータと整合性が採れなくなり、稼働後にシステム障害が発生する。
今からERPの導入を検討しようとしている企業の場合、「ERPの業務プロセスが合わない部分は、アドオンソフトの開発で乗り切りましょう」と提案してくるITベンダーがあったら要注意だ。そのベンダーはERPを理解していないので、依頼するのをやめたほうがいいかもしれない。
もし自社の業務プロセスにERPがどうしても合わないと評価するのであれば、そのERPを利用しないのが得策だ。自社開発に切り替えたり、自社に合う別のパッケージソフトを探したりするのが肝要だろう。合わないのに「世界中の企業が使っているから」「競合が使っているから」といった理由でERPを導入すると、アドオンの本数が膨大になり、開発の収拾がつかなくなる。その結果、「動かないERP」になってしまう。
この特集・連載の一覧

急伸「アンビエントIoT」、ウォルマートが数百万個 実は万博コンビニにも
米ウォルマートがIoT端末であるスマートラベルや電子棚札の導入を進めている。スマートラベルは、センサーや通信モジュールなどを搭載した小さなラベルで、荷物や商品を追跡可能にできる。2025年10月、ウォルマートはスマートラベルを数百万個導入すると発表した。

新宿駅西口に鉄道利用者優先のさらなる改良を期待
東京都による改良工事で新宿駅西口駅前広場が歩行者優先の空間に切り替わることを、2025年7月16日付の記事で報じた。切り替え完了直後の9月下旬、現地を見に行った。歩行者が地上で新宿駅西口から西新宿地区へ直進できる通路が、改良工事で新設され、駅前広場から延びているのを確認した。

Appierのチハン・ユーCEOとオードリー・タン氏に聞く、AIをフル活用する社会
AIをフルに活用したければ、そもそもどんな社会をつくりたいのか明確なビジョンが不可欠――。Appier Groupのチハン・ユーCEO兼共同創業者と、2024年まで台湾当局の初代デジタル担当政務委員(閣僚級)だったオードリー・タン氏へのインタビューでそんな印象が強くなった。
あなたにお薦め
今日のピックアップ

AIエージェント構築に不可欠な「MCP」、社内外のシステムの接続を標準化

スイッチ部門 アクセススイッチで6年ぶり首位交代、フロアとコアでHPEが存在感

富士通が「自前主義」を転換 IBMやNTTデータと連携模索、クラウド勘定系を拡販

SIerも逃げ出す「恐怖の案件」、DXなき基幹システム刷新につける薬はあるか

フォーティネットSSL-VPNからの移行の選択肢は3つ、接続性やコストに注意

脳の血管内に電極、AIで脳波を解釈 社会実装を目指すBMI研究の最新成果

正規の製品や機能を持ち込むサイバー攻撃「BYOX」、その脅威と対策を解説

デジタルノートアプリのGoodnotes創業者が語る「手書き×AI」の未来

旭鉄工社長の分身は「AIキムテツ」、DX成果外販で新たな事業モデルも目指す

通訳になるGoogle翻訳アプリの会話モード、英会話の自主練に役立つCopilot

「痛み」を共有するNTTドコモの新技術、6Gのユースケース開拓につながるか

耐久性とAI機能が向上した「Google Pixel 10 Pro Fold」、価格が最大のハードル
 注目記事
注目記事
おすすめのセミナー

ITリーダー養成180日実践塾 【第15期】
8回のセミナーでリーダーに求められる“コアスキル”を身につけ、180日間に渡り、講師のサポートの...

ITアーキテクト養成講座【第17期】
システム開発で一般的な「V字開発モデル」に沿って、上流工程から順を追ってITアーキテクトのタスク...

ITリーダー養成50日集中塾 【第21期】
ITの世界で活躍する女性がリーダーとしてさらに力を発揮できるようになるトレーニングプログラムです...

CIO養成講座 【第38期】
業種を問わず活用できる内容、また、幅広い年代・様々なキャリアを持つ男女ビジネスパーソンが参加し、...

コンサルスキル養成講座【第1期】
3日間の集中講義と演習によってAIで代替できない超上流工程のスキルを身に付け、コンサルタント/社...

「なぜなぜ分析」演習付きセミナー実践編
このセミナーでは「抜け・漏れ」と「論理的飛躍」の無い再発防止策を推進できる現場に必須の人材を育成...

生成AIとAIエージェントの導入&業務活用 実践講座
生成AIの基礎から応用までの講義と、ワークショップ「フレームワークを使った生成AIの自社活用アイ...

業務改革プロジェクトリーダー養成講座【第19期】
3日間の集中講義とワークショップで、事務改善と業務改革に必要な知識と手法が実践で即使えるノウハウ...
注目のイベント

日経BP 建設未来プロジェクト
2025年10月29日(水) 10:00~17:30

【10月30日】製造業の新規事業創出と構造改革を同時に実現するには? 現場と経営が一体で進める具体的な実践法
10月30日(木)

【11月11日】2025年10月に育児・介護休業法改正が施行、テレワークやペーパーレス化など環境整備が急務に
11月11日(火)

【11月12日】無限の可能性を引き出す「API」、AIエージェント同士がつながる未来を体験
11月12日(水)

IIFES 2025
2025年11月19日(水)-21日(金) 10:00~17:00

【11月21日】経理・財務を取り巻く環境は急速に変化、法改正・AIの進展・働き方の多様化でどう変わる?
2025年11月21日(金)

【11月28日】AIを活用したソフトウエア開発が急拡大、顕在化してきた重大リスクをどう回避するか
11月28日(金)

WOMAN EXPO 2025 Winter
2025年11月29日(土)10:00~17:30

スタンフォード式 生成AI BootCamp
2025年12月9日(火)~11日(木) ※ 事前学習(メール) 11月25日(火)~12月8日(月)、フィードバックデイ 12月19日(金)
おすすめの書籍

AIバブルの不都合な真実
AI幻想を見抜き、バブル崩壊後に勝ち残るAI導入・活用戦略を示します。

ランサムウエア攻撃との戦い方 セキュリティー担当者になったら読む本
攻撃の現状や手口、国内事例、対応方法、対策、歴史を徹底解説。本書を読めばランサムウエア攻撃を深く...

データマネジメント 仕組みづくりの教科書
AIの本格活用に不可欠なデータマネジメント。全社で取り組み各現場に定着させるにはどうすべきか。導...

さわって習得 Azure基礎からのインフラ構築
クラウドが普及拡大する中でより豊かな未来を創る礎としてAzureの基礎知識と実務的な操作方法・活...

ラズパイマガジン2025年秋号
ラズパイ電子工作で生成AIをどう使う?外部グラボをラズパイ5に接続して動かす!電子工作に活用する...

日経テクノロジー展望2026 未来をつくる100の技術
日経の専門誌編集長とラボ所長の約50人が、期待の技術を厳選して選出。2030年に向けた、期待のテ...