講談社ARTピース作品一覧
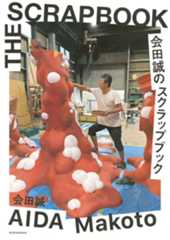
会田誠のスクラップブック
著:会田 誠
講談社ARTピース
現代社会の諸問題と格闘し、さまざまな波紋を広げてきた「全身美術家」会田誠。絵画、写真、立体、パフォーマンス、インスタレーション、都市計画まで。現代社会が抱える矛盾に真正面から向き合い、美術家としてのユーモアと共に作品を提示してきた。その歩みを自らの言葉で語り、制作の舞台裏を明かし、豊富な資料とともに振り返る、決定版的作品集。おもに2000年以降の作品を収録。図版750点、自作解説65,000字、オマケのツイート(現X)を880回分掲載。【まえがきより】今回、2000年以降の僕の活動をまとめる本を出すにあたって、「スクラップブック」と名乗るのが良かろう、という直感が働きました。大きな方向付けのない、バラバラな、未編集のような状態のまま示そう、という意図です。「スクラップブック」に似つかわしくない、(自分で言うのはおこがましいですが)マスターピースを狙って丁寧に描いたような絵画の中には、2000年以降のものでも、あえて収録しなかったものもあります。本のタイトルと内容が合致しているかどうかの判断は、読者の皆様にお任せしましょう。
電子あり
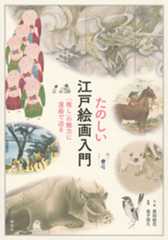
たのしい江戸絵画入門 「推し」の魅力に漫画で迫る
文・絵:長田 結花,監:金子 信久
講談社ARTピース
江戸絵画の深い深い“沼”にはまった漫画家が、7人の「推し」絵師の魅力を徹底解剖。多彩な造形に驚嘆し、細部に宿る面白みにしびれ、絵師たちの気持ちに思いを馳せます。美術を深く、自由に鑑賞するための、日本一ディープな美術入門書です。●円山応挙の「リアル」●長沢蘆雪の「やさしさ」●与謝蕪村の「ぎこちなさ」●岸駒の「かっこよさ」●歌川広重の「実験」●伊藤若冲の「かたち」●司馬江漢の「ファンタスティック」■コラム「好きな絵の話」中村芳中鍬形蕙斎俵屋宗達【この本について】●本書は、自らも絵を描く著者が、心から敬愛する7人の江戸時代の「推し」絵師の魅力を「エッセイ」「イラストレポート」「漫画」という3つの形式で紐解いてゆく、江戸時代絵画への入門書です。どこでも好きなところからお楽しみください。●紹介している絵の図版はすべて著者による模写です。やむをえず部分図となっている場合があります。オリジナル作品の作品名や所蔵などの情報は、それぞれのページに記載しています。●漫画は、絵師自身が残した日記をはじめとする様々な資料・文献を参考に、著者が想像力を羽ばたかせて描いたフィクションを含んでいます。
電子あり

代表作でわかる浮世絵BOX
著・編:太田記念美術館
講談社ARTピース
浮世絵は、江戸時代に江戸を中心として生まれた美術で、いまも世界中で高い人気を誇ります。その著名な絵師55人について、代表作を中心に紹介し、コンパクトに解説しました。絶対に知っておきたい浮世絵絵師と、その代表作が、まるわかりの一冊です。■本書で紹介する浮世絵絵師○前期菱川師宣、鳥居清信、鳥居清倍、懐月堂安度、宮川長春、奥村政信、西村重長、石川豊信、鳥居清満○中期鈴木春信、歌川豊春、礒田湖龍斎、一筆斎文調、鳥居清長、北尾重政、北尾政演、窪俊満、鍬形恵斎、勝川春章、東洲斎写楽、歌川豊国、歌川豊広、歌川国政、喜多川歌麿、鳥文斎栄之○後期葛飾北斎、葛飾応為、昇亭北寿、歌川国虎、菊川英山、溪斎英泉、歌川国貞、歌川広重、歌川国芳、歌川芳艶、歌泡芳藤、歌川芳虎、歌川芳員、歌川貞秀、歌川広景、○近代月岡芳年、落合芳幾、河鍋暁斎、豊原国周、三代歌川広重、楊洲周延、水野年方、小林清親、井上安治、小倉柳村、小原古邨(祥邨)、橋口五葉、川瀬巴水、伊東深水、吉田博■本書で紹介するおもな絵師の代表作菱川師宣『見返り美人図』 菱川師宣『衝立のかげ』 奥村政信『足袋の紐』鈴木春信『夜の梅』喜多川歌麿『歌撰恋之部 物思恋』葛飾北斎『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』歌川広重『名所江戸百景 亀戸梅屋舗』歌川国芳『猫と遊ぶ娘 団扇絵判錦絵』月岡芳年『大日本名将鑑 神武天皇』川瀬巴水『東京十二題 こま形河岸』■コラム春信のドラマ性出版プロデューサー・蔦屋重三郎寛政三美人と浮世絵■執筆赤木美智、日野原健司、渡邉晃(太田記念美術館)

江戸絵画お絵かき教室
著・編:府中市美術館
講談社ARTピース
府中市美術館『江戸絵画お絵かき教室』公式図録。江戸の名画はどう描かれたか。江戸時代の画家に入門したつもりで、描き方を解説。

子犬の絵画史 たのしい日本美術
著:金子 信久
講談社ARTピース
「かわいい子犬画」はどのように成立したのか中国・朝鮮から伝わり、応挙が完成させた子犬の絵は、蘆雪をはじめ多くの後継者を経て、近代へとつながっていく。子犬の絵に魅せられた学芸員がひもとく、初めての絵画史。応挙の子犬の絵がなかったら、生きる道はまた違っていたかもしれない。 ──「あとがき」より──円山応挙、長沢蘆雪、俵屋宗達、与謝蕪村、伊藤若冲……国内外の美術館・博物館、プライベートコレクションから選りすぐりの116点が大集合!一章 海の向こうの子犬の絵二章 日本の子犬の絵三章 犬の美術あれこれ

北斎 百鬼見参
著・編:すみだ北斎美術館
講談社ARTピース
すみだ北斎美術館「北斎 百鬼見参」展(2022年6月21日~8月28日)公式図録。初公開の肉筆画「道成寺図」をはじめ「百物語」シリーズなどで鬼才・北斎が鬼をどのように捉え、表現してきたかに迫る。人気作、肉筆画から版本まで……鬼才が描いた、異界への「恐れ」と「親しみ」「恐ろしい鬼」「哀しい鬼」「愛らしい鬼」時代を超えて跳梁跋扈する姿を、北斎の筆はどう捉えたか?北斎とその一門による、すみだ北斎美術館館蔵品を中心に、鬼才・北斎がどのように鬼を捉え、表現してきたかを紹介。第一章●鬼とはなにか第二章●鬼となった人、鬼にあった人第三章●神話・物語のなかの鬼第四章●親しまれる鬼

北斎 HOKUSAI 日新除魔図の世界
著・編:九州国立博物館
講談社ARTピース
2022年4月16日(土)~6月12日(日)開催特別展「北斎」展(九州国立博物館)公式図録。門外不出、九州国立博物館のみ公開を許された、重要文化財「日新除魔図」全219枚を一挙掲載する他、「冨嶽三十六景」、小布施の天井絵など代表作の数々とともに、画業とその素顔に迫る決定版!第一章これぞ、北斎 ー「真正の画工」への道のりー第二章素顔の北斎 ー日新除魔図の世界ー第三章名作誕生の秘密 ー北斎とゆかりの画家たち[特別公開]新出の摺物[特別公開]小布施の天井絵

仙厓BEST100 ARTBOX
著・編:出光美術館
講談社ARTピース
「面白い」「深い」「かわいい」……「厓画無法」で説いた人間賛歌。生涯に二千点にも及ぶ作品を残したといわれる仙厓義梵(1750-1837)。禅画の枠を超えた、「ゆるふわ」な世界観で、人生の機微とユーモアがあふれるその画や書は多くの人々を魅了し続けています。出光興産の創業者・出光佐三氏(1885-1981)は生涯をかけて作品を収集し、一千点あまりの日本最大の質と量を誇る仙厓作品のコレクションを築きました。その膨大なコレクションから、美術館が厳選し、解説。ベストオブベストを紹介します。1章:THE仙厓BEST102章:画報学びて不自由なり3章:仏の教え、禅の教え4章:人生訓は、ちょっと辛口で5章:「厓画無法」の世界6章:「ゆるさ」の効用7章:九州風土記--名所巡り8章:自在ーー無法の書の魅力9章:遺愛の品々
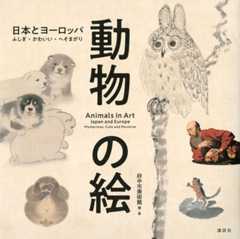
動物の絵 日本とヨーロッパ ふしぎ・かわいい・へそまがり
著・編:府中市美術館
講談社ARTピース
府中市美術館20周年記念『動物の絵 日本とヨーロッパ ふしぎ・かわいい・へそまがり』展公式図録。ゴーギャン、ピカソ、シャガール、若冲、応挙、光琳、宗達……動物絵画の「極め付き」全183点を掲載。描きたい。見たい。まみれたい。動物を見つめて、動物を描く。動物への「まなざし」で辿る、新しい美術史。日本とヨーロッパ。それぞれの土地で、人々は動物からどんな美術を作り出してきたのか。動物への思いが、別世界への扉を開く--府中市美術館 開館20周年記念「動物の絵 日本とヨーロッパ ふしぎ・かわいい・へそまがり」2021年9月18日(土)→11月28日(日)主な掲載作品:伊藤若冲「象と鯨図屏風」伊藤若冲「河豚と蛙の相撲図」俵屋宗達「狗子図」尾形光琳「鷺図」長沢蘆雪「十二支図」円山応挙「雪中狗子図」徳川家光「兎図」桂ゆき「作品」小倉遊亀「径」歌川国芳「金魚づくし いかだのり」ポール・ゴーギャン「小屋の前の犬、タヒチ」パブロ・ピカソ「仔羊をつれたポール、画家の息子、二歳」ギュスターブ・モロー「一角獣」オディロン・ルドン「ペガサスにのるミューズ」マルク・シャガール「翼のある馬」ルーラント・サーフェリー「神の救済に感謝するノア」

人体を描きたい人のための「美術解剖学」
著:金井 裕也
講談社ARTピース
【上達したい人のための「美術解剖学」!】人体をリアルに描くためには、骨や関節、そして筋の付き方といった解剖学的な知識が欠かせません。そういった基礎知識を踏まえたうえで、人体の動きや、体表にあらわれる凹凸を捉えることができれば、イラストは生き生きとしたものになるのです。本書は、人体の特徴や動きをつかむための【基礎編】と、動きのある人体を描くための【実践編】で構成されています。【基礎編】では、精密に描かれた解剖学的なイラストで、人体とその動きに対する理解を深めることができます。そして【実践編】では、「動きの少ないポーズ」から「動きの大きいポーズ」までを網羅。「動き」を描くコツがわかります。また、人体の構造を確認できるよう、骨・筋のイラストが添えられています。デッサン、コミック、アニメーションなどに携わる人、イラストの上達を目指す人、必携の1冊です。《本書の内容》【基礎編】第1章 人体の基礎知識と特徴 ――人体を描くために知っておくべき基本的な解剖学の知識と、人体の特徴のつかみ方 体表から触れるポイント/全身の筋/全身の骨/全身の関節/男性と女性の違い ほか第2章 全身の筋とその動き ――体表にあらわれる筋はどこについているのか、そして、筋は体表にどのような凹凸をもたらしているのか 表情筋/頸部の筋/胸部・背部の筋/腹部・背部の筋/殿部の筋/肩の筋/上腕の筋/前腕の筋/手の筋/手のいろいろな動き/大腿の筋/下腿の筋/足の筋/下肢のいろいろな動き【実践編】第3章 人体のさまざまな動きを描く ――動きの少ないポーズから動きの大きいポーズまで、「動きのある人体」を描くコツ 〔動きの小さいポーズ〕立つ/歩く/階段を上る/座る/寝る/食べる/飲む/スマホを使う/本を読む/手を洗う/着替える/かばんを持つ/拍手/手をつなぐ ほか 〔動きの大きいポーズ〕走る/ジャンプ/野球/サッカー/テニス/バスケットボール/バレーボール/卓球 ほか
電子あり

鳥獣戯画の国 たのしい日本美術
著:金子 信久
講談社ARTピース
国宝、鳥獣人物戯画のレジェンドとしての輝き。私たちの心を遊ばせてきた、「楽しまれてきた歴史」。この絵巻が生まれるべくして生まれた日本という国を眺めてみよう。残された様々な模写だけでなく、伊藤若冲、歌川国芳、河鍋暁齋、曽我蕭白、森狙仙……動物が好きすぎる絵師たちのユニークな作品に受け継がれた、--鳥獣戯画--の遺伝子。それは昔話や伝説の中でも確認できます。「伝説的なおかしな動物の絵」が、どのように日本人の心をとらえ、動物絵画のスタイルとして定着してきたか。府中市美術館でのユニークな企画で注目を集める著者による、新しい動物絵画史。かわいくて、愉快で、どこかおかしい--そんな愛おしい作品を多数掲載。第一章 --鳥獣戯画--の楽しさ第二章 --鳥獣戯画--の子どもたち第三章 動物ものがたり第四章 不思議と夢想 -ウサギとキツネ-第五章 動物たちの心

THE北斎 冨嶽三十六景ARTBOX
著・編:すみだ北斎美術館(奥田敦子)
講談社ARTピース
すみだ北斎美術館、初のオフィシャルブック。当館所蔵の冨嶽三十六景すべてをコンパクトな判型にまとめ、作品のディテールを楽しめるガイドブックです。「空間を構成する」「○×△で作られた世界」「驚異の自然」「形のないものを捉える」「イリュージョンを仕掛ける」「超絶表現」という6つの章に分け、さまざまな切り口で、生涯の代表作にして最高傑作「冨嶽三十六景」の魅力を紹介します。天才の技術と着想が極まった全46図を堪能できる一冊です。第一章 空間を構成する第二章 ○×△で作られた世界第三章 驚異の自然第四章 形のないものを捉える第五章 イリュージョンを仕掛ける第六章 超絶表現・全46図一覧&MAP付き

「スペインの最も美しい村」全踏破の旅
著:吉村 和敏
講談社ARTピース
シリーズ第4弾。「最も美しい村」連合公認の79村(2019年11月現在)を全踏破。圧倒的な美しさで村々の息遣いを切り取る。「スペインの最も美しい村」とは2011年に「スペインの最も美しい村」協会が設立され活動を開始。人口15000人以下(歴史地区の人口は5000人以下)であること、建築的遺産または自然遺産があることなどを条件に、村内の環境、宿泊施設、案内板に至るまで厳正に審査し、登録を認定している。2019年11月末時点で、79村が認定されている。白い村、石畳の村、城壁の村……絶景と歴史遺産を巡る旅どの村も歴史ある石積みや木組みの家屋が寄り添うように建ち並び、立派な聖堂を持っていた。美しい景観やまだ知らぬ歴史文化に新鮮な驚きとときめきばかり。旅が終わる頃には心が高揚感で満たされていた――写真家吉村和敏が、取材期間3年をかけて訪ね歩いた、知られざるスペイン。雄大な自然と、激動の歴史を静かに伝える美しい村々を活写する!
電子あり

地獄絵ARTBOX
著:加須屋 誠
講談社ARTピース
「地獄」とは何か? 地獄絵には何が描かれているのか? 恐怖、畏敬、信心、ユーモア……その魅力に様々な角度からアプローチ!国宝「六道絵」「地獄草紙」ほか、数多の作品の図版から、絵画に描かれたその恐ろしくも魅惑的な「地獄」の世界を解説します。●人は死んだらどこへ行くのか? 地獄の歩き方 -長岳寺「大地獄図」でめぐる「あの世」●そもそも「地獄」って何でしょう?●地獄絵を鑑賞するための豆知識 ー六道の輪廻、八大地獄●地獄絵鑑賞のポイント●聖衆来迎寺の「六道絵」●後白河法皇と地獄絵巻●地獄絵の集大成「熊野観心十界図」●十王信仰●地獄の鬼たち●九相図が見せる死後の現実etc.

へそまがり日本美術 禅画からヘタウマまで
著・編:府中市美術館
講談社ARTピース
府中市美術館開催『へそまがり日本美術 禅画からヘタウマまで』展」(2019年3月16日~5月12日)公式図録。素朴、稚拙、ヘタウマ、突拍子もない造形……決してきれいとは言えないけれどなぜか心惹かれる。日本人の「へそまがりな感性」が生んだ、もうひとつの日本美術史。毎年同時期に開催される府中市美術館の「春の江戸絵画まつり」。2019年のテーマは「へそまがり」。中世の水墨画から江戸絵画、そして現代のヘタウマ漫画まで。不可解な描写、技巧を否定したかのようなゆるい味わい……「へそまがり」な感性から生み出された、常識を超えた、美術史に新たな視点を与える展覧会です。また、同展覧会は長沢蘆雪、伊藤若冲を含む44点もの新発見作品が出品される予定で、さらに、徳川家光、家綱など、お殿様の絵も多数展示され、その「ゆるカワ」な世界観が話題沸騰! 2019年注目の日本美術展となっています。同展担当学芸員金子信久氏をメインの執筆者に、単なる作品解説にとどまらない、エキサイティングな日本美術評論としてお楽しみいただける一冊です。

ミズノ先生の仏像のみかた
著:水野 敬三郎
講談社ARTピース
仏像研究の第一人者がやさしく語るいちばん詳しくておもしろい「仏像のみかた」半世紀以上前から第一線で仏像を研究してきた著者が、仏像のみかたや考え方を対話形式でやさしく解説。目、耳、表情、体型、衣、彩色……など、仏像をみるときのポイントや、時代ごとの特徴をイラストとともにわかりやすく説明しています。銘文や納入品、技法、仏師などについても詳しく紹介。さまざまな側面から仏像について語っています。これまでの仏像本とは一線を画す内容で、初心者にはもちろん、仏像に詳しい方にも楽しんでいただける一冊です。【目次】序章 仏像って、どうみたらいいの?第一章 まずは仏像の顔からみる第二章 少し離れて仏像の全体をみる第三章 もっと離れて仏像のまわりもみる第四章 仏像がどうやってつくられたかを知る第五章 仏像のなかをのぞいてみる第六章 仏像をつくった人たちについて知る日本仏像史年表「はじめに」より如来は悟りを開いた仏陀の姿、菩薩は悟りを目指して修行している姿、明王は怒りの姿で人々を導く密教の仏、天は仏教を守護する神様……それぞれにかたちのきまりがあります。しかし、これについては多く出版されている仏像入門書にまかせて、ここでは仏像の作者がどのような仕方で、何を表現しようとしたのか、どのような祈りにこたえようとしたのか、それに迫る手立てとしての「仏像のみかた」について考えてみることにします。(中略)教室で講義するような堅苦しい感じではなく、お茶やときにはお酒を飲みながら気軽に話しましたが、ときどき脱線しそうになったり、少し専門的なところもあったりします。難しいと思うところは、はしょっていただいてもかまいません。とにかく最初から最後まで通して読んでいただければ、仏像のみかたにいろいろあることがわかり、こんな角度からみるのもおもしろいかなと思っていただけると思います。

へんな西洋絵画
著:山田 五郎
講談社ARTピース
可愛くない子どもたち、どう見てもおかしな動物……偉大な西洋画家たちが描いた“へんな絵”で、笑って学ぶアート入門誰もが知る傑作から、知る人ぞ知る名画まで、選りすぐりの“へんな絵”120点を掲載。美術評論家・山田五郎氏が、絵につっこみを入れながら、どうして「へん」なのかを真面目に解説しています。笑いながら読んでいるうちに西洋美術の知識が身につく、これまでにない一冊。純粋におもしろい絵が見たい人にも、西洋美術の教養を身に付けたい人にもおすすめです!【目次】・可愛くない子どもたち・なにぶん昔のことですから・見たことのない未確認生物[UMA]たち・小さいおじさん、大きいおばさん・多すぎ、描きすぎ、細かすぎ・あえてそう描く、その意味は?・自分で自分をへんに描く「西洋絵画史とへんな絵の流れ」年表つき
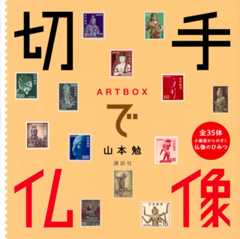
ARTBOX 切手で仏像
著:山本 勉
講談社ARTピース
切手という極小の画面からのぞく「仏像のひみつ」郵便切手のモチーフとなった仏像は、日本人から長く愛されてきた名品ばかり。本書では、その仏像切手を題材にして仏像の歴史や特徴をやさしく解説する、ひと味違った仏像入門書です。切手の薀蓄コラムは、「切手の博物館」学芸員・田辺龍太さんが担当。懐かしの切手や珍しい切手を原寸と拡大図版で紹介しているので、切手ファンの方にもおすすめです。

横山大観ART BOX
著:佐藤 志乃
講談社ARTピース
掌から溢れ出る巨匠の世界。横山大観の代表作からめったに見ることができない作品まで、その生涯を辿りながら鑑賞できるお得な一冊!

藤田嗣治の少女
絵:藤田 嗣治,編:会田 誠
講談社ARTピース
藤田嗣治の「少女」を会田誠が語る! 生涯で描いたたくさんの少女画から、会田誠が選んだ85点を掲載。秋田、ランス訪問記も。