¥1,320 税込
| 獲得予定ポイント: | +74 pt (6%) |
期間限定ポイント |
上のボタンを押すとKindleストア利用規約に同意したものとみなされます。支払方法及び返品等についてはこちら。
これらのプロモーションはこの商品に適用されます:
一部のプロモーションは他のセールと組み合わせることができますが、それ以外のプロモーションは組み合わせることはできません。詳細については、これらのプロモーションに関連する規約をご覧ください。
を購読しました。 続刊の配信が可能になってから24時間以内に予約注文します。最新刊がリリースされると、予約注文期間中に利用可能な最低価格がデフォルトで設定している支払い方法に請求されます。
「メンバーシップおよび購読」で、支払い方法や端末の更新、続刊のスキップやキャンセルができます。
エラーが発生しました。 エラーのため、お客様の定期購読を処理できませんでした。更新してもう一度やり直してください。

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

天皇の歴史4 天皇と中世の武家 (講談社学術文庫) Kindle版
このページの読み込み中に問題が発生しました。もう一度試してください。
12世紀末、日本史上初めての本格的な内戦、治承・寿永の内乱の結果、新しい武士の政治組織、鎌倉幕府が誕生。政治体制は、それまでの朝廷の単独支配から、明治維新まで続く朝廷・幕府体制へと大きく変化する。父子一系の皇統をめぐる朝廷の動揺と、朝廷再建を図る源頼朝、後醍醐天皇、足利義満の構想など、朝廷・幕府体制の展開を探りながら、古典を鑑として秩序を求めた人々の営為を明らかにする。
この本はファイルサイズが大きいため、ダウンロードに時間がかかる場合があります。Kindle端末では、この本を3G接続でダウンロードすることができませんので、Wi-Fiネットワークをご利用ください。
販売: 株式会社 講談社
まとめ買い
シリーズの詳細を見るこのまとめ買いには3冊が含まれます。
このまとめ買いには5冊が含まれます。
このまとめ買いには1-10冊のうち10冊が含まれます。
エラーが発生しました。
お買い得タイトル
あなたの購入および読書履歴からのおすすめ本シリーズ (全10冊)
ページ1 /1最初に戻る
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ:1 /1最初に戻る
商品の説明
著者について
河内 祥輔
1943年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退。北海道大学教授、法政大学教授を経て現在、北海道大学名誉教授。専攻は日本中世史。主な著書に『日本中世の朝廷・幕府体制』『保元の乱・平治の乱』『中世の天皇観』などがある。
新田 一郎
1960年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退。専攻は日本法制史・中世史。現在、東京大学教授。主な著書に『日本中世の社会と法』『日本の歴史11巻 太平記の時代』『中世に国家はあったか』『相撲の歴史』。
1943年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退。北海道大学教授、法政大学教授を経て現在、北海道大学名誉教授。専攻は日本中世史。主な著書に『日本中世の朝廷・幕府体制』『保元の乱・平治の乱』『中世の天皇観』などがある。
新田 一郎
1960年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退。専攻は日本法制史・中世史。現在、東京大学教授。主な著書に『日本中世の社会と法』『日本の歴史11巻 太平記の時代』『中世に国家はあったか』『相撲の歴史』。
登録情報
- ASIN : B07B7JS8BR
- 出版社 : 講談社 (2018/3/9)
- 発売日 : 2018/3/9
- 言語 : 日本語
- ファイルサイズ : 22.9 MB
- Text-to-Speech(テキスト読み上げ機能) : 有効
- X-Ray : 有効
- Word Wise : 有効にされていません
- 本の長さ : 412ページ
- Amazon 売れ筋ランキング: Kindleストア - 74,255位 (Kindleストアの売れ筋ランキングを見る)
- 歴史学 (Kindleストア) - 230位
- 歴史学 (本) - 284位
- カスタマーレビュー:
著者について
著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。
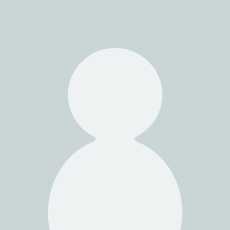
Brief content visible, double tap to read full content.
Full content visible, double tap to read brief content.
著者の本をもっと見つけたり、似たような著者を調べたり、おすすめの本を読んだりできます。
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中にエラーが発生しました。ページを再読み込みしてください。
- 2018年7月8日に日本でレビュー済みフォーマット: 文庫Amazonで購入河内氏執筆の第一部では、
正統(『神皇正統記』でいわれる「しょうとう」)
がキーワードになっています。
朝廷の歴史は、
「正統」が存在する安定期と、それが不明確な
不安定期を繰り返している、という視点から
鎌倉時代が叙述されています。
教科書的な歴史とは かなり違った印象ですが、
これはこれで 興味深く集中して読めました。 - 2011年6月14日に日本でレビュー済みフォーマット: 単行本Amazonで購入2部構成の本書。第一部が平安時代の総括と鎌倉時代、第二部が室町時代で筆者も違う。第一部と第二部が良くも悪くも好対照をなしている。
第一部は歴史に丁寧に寄り添う記述、第二部はこの時代の世界観を論じる記述に特徴あり、といったらいいだろうか。
第一部はさすが編集委員だけあって、書き方に工夫がみられる。
とくに、安定期と不安定期が交互に到来していたという平安時代の総括は、そうだったのか!と目からウロコ。このことを念頭に置くと、鎌倉時代以降がよくわかる。皇位継承における正統(しょうとう。せいとうと読んだ人は是非とも本書を紐解くべし)の意味がよくわかった。
正統は、その状況を作り出して初めて得られるものだった。歴代天皇は望む皇位継承をはたすために、正統を獲得すべく日夜奮闘したのですね。いやらしくもありますが…。
第二部は、きわめてクセのある個性的な書き方。媒介変数とかエントロピーとか、えっと思うような用語が頻出する。ちょっと乱暴じゃないかと思うが、我慢して読み進めると、味わい深いアフォリズムに出会う。
いわく「世界のありように、目に見える具体的な形を与えるのは、日ごと年ごとに定型を以て繰り返される儀礼である」。
いわく「世界の儀礼的中心としての」天皇。
いわく「世界観の問題を凍結することによって、政治は徹底して現世化され、形式的儀礼の次元で世界を統合する」。
うーむ、深い…。だが、ぶっ飛んでいないか?
というわけで、第一部と第二部はそれぞれに独自性がある反面、両者の接続はあまりうまくいっていない。同じ時代をこの二人の筆者が書き、それらの読み比べをしたら面白いかもしれない。 - 2018年5月22日に日本でレビュー済みフォーマット: 文庫56頁までだけでも、平城・嵯峨・淳和から平清盛の台頭まで全てを天皇家の「正統」を巡る争いだと一括する見方。とてもイデオロギー的で、話としては面白いけれど、歴史学としては違和感ばかりで読み進めています。出典を書く方式ならまだしも、それもなし。
この本は、「天皇の歴史」というシリーズの1冊。同じ講談社学術文庫の「日本の歴史」が、特に桜井英治『室町人の精神』が非常に面白かっただけに、それと同じレベルを期待して買ったのですが…かなり不安を感じる内容です。 - 2011年12月16日に日本でレビュー済みフォーマット: 単行本後半の新田一郎氏は、意味もなく難しい言葉を使って自己満足の文章に
堕している。
前派の河内氏の記載が、歴史の叙述と分析の程よいつり合いを保ちな
がらなかなかに読ませるのに対し、後半の書きぶりは全く時代遅れの感を
与える。学者の世界はよく知らないが、たぶんそれなりの大家とされてい
るのだろう。しかし、こんな文章が許されると思っているとしたら、甘やか
されているのではないか。 - 2018年7月8日に日本でレビュー済みフォーマット: 文庫このシリーズは6まで読んだが一番レベルが低い。崇徳が白河上皇の子である、という説を俗説として否定しているが根拠を示していない。鳥羽がなぜ崇徳を嫌っていたか、はこの時代のキーであるはず。それを史料も示さず「鳥羽の白河に対する反発心で理解出来る」とするのは物足りない。頼朝が奥州藤原氏を討ちたいがためにまず義経に謀反するよう仕向ける、その為に義経にわざと失敗する手筈の暗殺団を送り込む、という説はもはや陰謀論である。これも根拠を示していない。公暁による実朝暗殺は様々な黒幕説は否定し単独犯だそうである。理由は実朝が死んでも得をする人間がいないから、だそうである。以下疑問点はいくらもあるが書ききれぬ。
- 2011年6月16日に日本でレビュー済みフォーマット: 単行本少なくともこのシリーズの全体編成には相当の無理があったのではないのか。これが一読しての感想だった。
「天皇と中世の武家」とタイトルされたこの本が対象とするのは平安末の源平争乱時代から室町幕府滅亡まで、11世紀半ばから16世紀終盤にかけての約500年に相当する。そこには「武者の世になりにける」(愚管抄)に始まり「親政」そして「武家政治の再生」「権力装置としての天皇の失墜」といった事象が重層的かつ波状的に生じていることも確かである。
歴史の研究者として歴史学の成果を一般書に記述するならば、「天皇」を1つのメルマクールなりスポットとしてこの時代を概括的な視点から扱うためには少なくとも「権力装置としての天皇」と「権威装置としての天皇」が分化しているのか或いは未分化なのか、それを「政治的権力」が自らの胎内に「どの様に組み込んでいくか」が追尾される必要がある。
二部構成のスタイルをとる本書の後半部分を担当する新田一郎はかつて今谷明との間で「足利義満の王権」を巡り激しい論争を繰り広げたがその着地点は曖昧にされたままで未だ結論を見てはいない。少なくとも新田は「中世に国家はあったのか」と従来の「中世国家論」に対する疑問を立て、それに対する帰結点を提示するとの命題を課しながらその検証を放棄したままで現在に至る不毛な時間を送ってきたにすぎない。それが本書でも繰り返されている。
東大相撲部の顧問として「相撲」に関してマスメディアに登場し様々な意見を彼方此方で行うことは「趣味」として許されるが、本業としての「歴史学」に成果を残せないのでは最早彼に期待するモノはない、といっても言い過ぎだろうか。 - 2011年6月27日に日本でレビュー済みフォーマット: 単行本最近同じ講談社から出た「日本の歴史」の六巻は、大体おなじ範囲を扱っているけど、そちらの記述は大胆に資料の裏まで読んでいて面白かった。その直後に読んだこともあり、権力闘争に起因する白黒はっきりした人間関係が当然の前提とされている記述は退屈だった。
そんなに単純なものじゃないと思う。
頭が硬くてつまらない。
天皇をメインテーマにするのに、こういう学者にやらせるのは無理があるのでは。


![Amazonフレッシュ ブラックフライデー 特選セール 最大50%OFF [エリア限定]](/image.pl?url=https%3a%2f%2fm.media-amazon.com%2fimages%2fI%2f219n6C1AfQL.jpg&f=jpg&w=240)




























