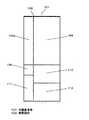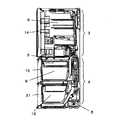JP2007147224A - 冷蔵庫 - Google Patents
冷蔵庫Download PDFInfo
- Publication number
- JP2007147224A JP2007147224AJP2005345683AJP2005345683AJP2007147224AJP 2007147224 AJP2007147224 AJP 2007147224AJP 2005345683 AJP2005345683 AJP 2005345683AJP 2005345683 AJP2005345683 AJP 2005345683AJP 2007147224 AJP2007147224 AJP 2007147224A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- door
- storage
- refrigerator
- pull
- compartment
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Withdrawn
Links
Images
Landscapes
- Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
Abstract
Description
本発明は、冷蔵庫の各貯蔵室の配置及び扉に関するものである。
従来、左右に分割された貯蔵室を区画している冷蔵庫において、特許文献1に参照するように、最下段の貯蔵室が左右に分割されて引き出し式扉で構成されているものが提案されている。
図6、図7は特許文献1に記載された従来の冷蔵庫を示すものである。図6は従来の冷蔵庫の扉を開けた状態の斜視図、図7は従来の冷蔵庫の縦断面図である。
図6、図7に示すように2は冷蔵庫本体1内を上下に区画する断熱区画壁であり、上部に上部区画3、下部に下部区画4を形成し、冷凍サイクルの圧縮機5は下部区画4の最下段の後方領域に収納されている。6は上部区画3内を左右に区画する第1の区画壁であり、7は下部区画4内を左右に区画する第2の区画壁である。8は第1の区画壁6により一側に形成された冷蔵室、9は冷蔵室8の下部に区画壁10を挟んで形成された野菜室である。11は第1の区画壁6により他側に形成されたボトル収納室である。12は第2の区画壁7により一側に形成された冷凍室、13は他側に形成された製氷室である。
冷蔵室8の開口面には開閉自在に取り付けられたヒンジ開閉式扉14が設けられている。野菜室9は開口面に開閉自在に取り付けられた引出し式扉15を設けており、室内側の収納容器(図示せず)を一体に引き出せるように構成されている。
ボトル収納室11は開口面に開閉自在に取り付けられた引出し式扉16を設けており、室内側の収納容器17、18、19、20を一体に引き出せるように構成されている。また、冷凍室11は開口面に開閉自在に取り付けられた引出し式扉21を設けており、室内側の収納容器(図示せず)を一体に引き出せるよう構成されている。製氷室12は開口面に開閉自在に取り付けられた引出し式扉22を設けており、室内側の収納容器(図示せず)を一体に引き出せるように構成されている。
特開2001−263913号公報
しかしながら、上記従来の構成では、従来一般的であった下部区画4の後方に圧縮機を収納することで、その設置容積分貯蔵室側に突出し、下部区画4の収納スペースを減少させる。また、貯蔵室を左右に分割することによって、左右を仕切る仕切壁等が必要となり、さらに収納スペースの減少に繋がるという課題を有していた。
本発明は、上記従来の課題を解決するもので、冷蔵庫本体1の無効スペースをうまく活用し、下部区画4の収納スペースを増加させることはもちろんのこと、引き出し式扉の構成によって貯蔵室に収納された食品を引き出して奥まで出し入れが非常にし易い冷蔵庫を提供することを目的とする。
冷蔵庫本体を形成する断熱箱体と、複数の貯蔵室と、前記複数の貯蔵室のそれぞれに前面開口部を塞ぐ扉と、前記断熱箱体の天面後方に設置された圧縮機とを備え、前記複数の貯蔵室のうち、前記冷蔵庫本体の最下段に位置する貯蔵室は左右に区画して形成され、少なくともその一方を引き出し式扉で構成するものである。
これによって、下部区画をさらに左右の領域に区画しても収納スペースが大きく減少することなく構成することができ、かつ引き出し式扉によって奥まで取り出しやすくすることができる。
本発明の冷蔵庫は、断熱箱体の天面後方に圧縮機を収納することで、下部区画の収納スペースを増大させた上で、左右に区画することで収納物の形状や目的に応じた区画収納をすることができる。
また引き出し式扉で構成することで、奥に収納している収納物を手前に簡単に引き出すことができるため、収納物が出し入れしやすい構造にすることができる。
また、左右に分割し引き出し式扉の幅方向の寸法を小さくすることで、扉を引き出した時に左右両側から収納物を取り出せるという利点も有する。
請求項1に記載の発明は、冷蔵庫本体を形成する断熱箱体と、複数の貯蔵室と、前記複数の貯蔵室のそれぞれに前面開口部を塞ぐ扉と、前記断熱箱体の天面後方に設置された圧縮機とを備え、前記複数の貯蔵室のうち、前記冷蔵庫本体の最下段に位置する貯蔵室は左右に区画して形成され、少なくともその一方を引き出し式扉で構成するものであり、断熱箱体の天面後方に圧縮機を収納することで、下部区画の収納スペースを増大させた上で、最下段の貯蔵室を左右に分割することで収納物の形状や目的に応じた区画収納をすることができる。また引き出し式扉で構成することで、奥に収納している収納物を手前に簡単に引き出すことができるため、収納物が出し入れしやすい構造にすることができる。
請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、前記引き出し式扉は、前記最下段の貯蔵室の他方よりも幅方向で小さくしたものであり、左右に分割し幅方向の寸法を小さくすることで、収納物をある程度重ねずに収納することができ、扉を引き出した時に左右両側から収納物を取り出せるという利点も有する。また、扉自体を小さくすることで、その操作感を軽くしスムーズ性を向上させることも可能となる。
請求項3に記載の発明は、請求項1または2に記載の発明において、前記引き出し式扉は、奥行き方向で略全体を引き出せる構成にしたものであり、奥に収納している収納物も完全に手前にまで引き出すことができるので、さらに出し入れがしやすい。また収納物を確実に目でとらえることができるので、扉を開放する時間が短くて済み冷気漏れを抑制し、省エネにも繋がる。
請求項4に記載の発明は、請求項2または3に記載の発明において、前記引き出し式扉は、前記断熱箱体の側壁に摺動部を備え、前後方向へ摺動させるよう構成したものであり、従来からの両壁で支持する構成ではなく、摺動させるレール等が片側のみで構成するので、その片側分の無効スペースを活用し、収納スペースを増大することができる。
また、隣の貯蔵室は相対的に同じ温度帯の貯蔵室であれば、その貯蔵室との間に仕切壁を設けることなく引き出し式扉を構成できるので、さらなる収納スペースの拡大と見た目の広々感を持つことができて貯蔵室内の視認性やデザイン性も向上するという利点を有する。
請求項5に記載の発明は、請求項1から4のいずれか一項に記載の発明において、前記断熱箱体を断熱された仕切壁によって上部区画と、下部区画とに区画形成し、前記下部区画は前面開口を塞ぐ扉によって左右の領域に区画され、前記左右の領域のいずれか一方の領域をさらに前面開口を塞ぐ扉によって上下の領域に区画するとともに、前記上下の領域を引き出し式扉で構成したものであり、従来下後方に存在した圧縮機による貯蔵室への突出代が極端に小さくなることで、貯蔵室の背面側がフラットに近い形状になり、収納容器の形状を直方体に近い形状にすることができ、その貯蔵室を上下に分割しても上下共に収納スペースを増大することができる。さらに、区分収納による使い分けができ、必要に応じた扉開閉による温度上昇の低減が図れ、省エネにも繋がる。
請求項6に記載の発明は、請求項5に記載の発明において、前記上部区画を冷蔵温度帯の貯蔵室とし、前記下部区画の前記引き出し式扉を備えた貯蔵室を冷凍温度帯の貯蔵室とし、前記引き出し式扉の上領域を製氷室としたものであり、製氷室の上端を冷蔵庫本体の略中央付近に位置させることで、腰をかがめることなく楽な姿勢で取り出すことができとともに、他の部屋と独立させることで、冷凍収納物と氷の使い分けができ、臭い移りを防止したキレイな氷を提供するとともに、必要に応じた扉開閉による温度上昇の低減が図れ、省エネにも繋がる。
請求項7に記載の発明は、請求項5または6に記載の発明において、前記他方の領域を上下の領域に区画するとともに、その前面開口を引き出し式扉で構成し、その上方を野菜室とし、下方を冷凍室で形成したものであり、野菜室の上端を冷蔵庫本体の略中央付近に位置させることで、腰をかがめることなく楽な姿勢で取り出すことができとともに、使用頻度及び収納物による適切な寸法に応じた貯蔵室のレイアウトと使いやすい扉の開閉状態の組み合わせが実現でき、冷蔵庫全体としての使い勝手が高まる。また、引き出した時に左右両側から収納物を容易に出し入れできる利便性も有する。
請求項8に記載の発明は、請求項6または7に記載の発明において、前記上部区画の貯蔵室は、前面開口を塞ぐ扉を有し、その扉は前記製氷室の幅の延直線で分割させたものであり、最上部の貯蔵室の扉を分割することで、区画収納ができるとともに必要に応じた扉開閉による温度上昇の低減が図れ、省エネにも繋がる。また、冷蔵庫本体の上下方向の全高で縦ラインが一直線で構成することができるので、高級感とデザイン性の向上が図れる。
以下、本発明による冷蔵庫の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の形態によってこの発明が限定されるものではない。
(実施の形態1)
以下、本発明の実施の形態1を図1から図5に基づいて説明する。図1は本発明の実施の形態1における冷蔵庫の正面図、図2は同実施の形態における冷蔵庫の縦断面図、図3は同実施の形態における冷蔵庫の扉を開けた時の斜視図、図4は同実施の形態における冷蔵庫の天面後方の分解斜視図、図5は同実施の形態における冷蔵庫の引き出し式扉を引き出した時の上から見た図である。
以下、本発明の実施の形態1を図1から図5に基づいて説明する。図1は本発明の実施の形態1における冷蔵庫の正面図、図2は同実施の形態における冷蔵庫の縦断面図、図3は同実施の形態における冷蔵庫の扉を開けた時の斜視図、図4は同実施の形態における冷蔵庫の天面後方の分解斜視図、図5は同実施の形態における冷蔵庫の引き出し式扉を引き出した時の上から見た図である。
図において、冷蔵庫本体101は断熱箱体102内に複数に区画された貯蔵室を有しており、上部より冷蔵室103、製氷室104及びこの製氷室104に並設された野菜室105、第一の冷凍室106及びこの第一の冷凍室106に並設された第二の冷凍室107の順に配置されている。
各貯蔵室の前面開口部には、例えばウレタンのような発泡断熱材を発泡充填した断熱扉が設けられ、冷蔵室103には回転式の扉108、製氷室104、野菜室105、第一の冷凍室106、第二の冷凍室107には、それぞれ引き出し式の扉109、110、111、112が設けられている。冷蔵室103は収納形態によって左右で扉を分割し、双方を内側から外側に開く観音開き式扉や一方を引き出し式扉で構成することもある。
断熱箱体102は、ABSなどの樹脂体を真空成型した内箱113とプリコート鋼板などの金属材料を用いた外箱114とで構成された空間に発泡断熱材115を注入してなる断熱壁を備えている。ここで、発泡断熱材115はたとえば硬質ウレタンフォームやフェノールフォームやスチレンフォームなどが用いられる。発泡材としてはハイドロカーボン系のシクロペンタンを用いると、温暖化防止の観点でさらによい。
また、各貯蔵室を区画形成するための仕切壁を備えており、例えば冷蔵室103と製氷室104、野菜室105とを区画するための仕切壁116を備え、断熱箱体102を上部区画117と下部区画118に区画形成している。下部区画118はさらに左右に区画された左側の領域には上から順に製氷室104、第一の冷凍室106、一方右側の領域には上から順に野菜室105、第二の冷凍室107を形成している。
次に、断熱箱体102の各貯蔵室について説明する。
冷蔵室103は冷蔵保存のために凍らない温度を下限に通常1〜5℃で設定されている。貯蔵室内は上方を圧縮機120を収納するための凹み部が突出して形成され、食品などを整理して収納するための複数の棚121を設けている。最下段には肉魚などの保鮮性向上のためのチルドケース122を設け比較的低めの温度、たとえば−3〜1℃で設定されている。
製氷室104は、氷を生成して貯留するために通常−18℃で設定される。庫内は氷を生成するための製氷機構(図示せず)を設け、氷を貯留する貯氷容器(図示せず)を収容している。
野菜室105は、冷蔵室103と同等もしくは若干高い温度設定の2℃〜7℃とすることが一般的で、低温にするほど葉野菜の鮮度を長期間維持することが可能である。庫内は野菜などの食品を整理して収納できる野菜室容器124を収容している。
第一の冷凍室106及び第二の冷凍室107は、冷凍保存のために通常−22〜−18℃で設定されているが、冷凍保存状態の向上のために、たとえば−30や−25℃の低温で設定されることもある。庫内は食品を整理して収納できる冷凍室容器125を収容している。ここでは第一の冷凍室106は第二の冷凍室107よりも幅方向で小さく形成し、高さ方向に長い引き出し扉となっているが、両室をほぼ中央付近で区画した構成も考えられる。
また、第一の冷凍室106の引き出し式扉111は、手前に引き出せるような摺動部材123で前後方向に摺動させている。本実施の形態では、断熱箱体102の左側の断熱壁に摺動部材123としてのレールを上下に支持固定し、引き出し式扉111と連結させているが、一般的に使われる左右の壁に摺動部材123を支持固定しても構わない。
野菜室105と第二の冷凍室107の背面に冷却室130が設けられ、冷却室130は断熱性を有する仕切壁131で野菜室105及び第二の冷凍室107とを仕切っている。
冷却室130には、庫内の空気を熱交換させて冷気に変換する蒸発器132と、各貯蔵室に冷気を送るための冷却ファン133をその上方に位置させ、冷却時に蒸発器132に付着する霜を除霜するためのヒータなどで構成された除霜装置134が備えられている。また、除霜された水を貯留するための蒸発皿135は、断熱箱体102の底面付近に配置されるよう構成されている。
次に、断熱箱体102の天面部について説明する。
断熱箱体102の天面後方のコーナー部には、冷蔵室103の庫内側に突出する形で凹ませた機械室136が形成されている。機械室136は、樹脂成型で形成された機械室の外郭137を鋼板製の外箱114を切り欠いた箇所に嵌めこんだ形で係合して接合して形成され、その内部には、機械室の外郭137の底面に載置された圧縮機120、凝縮器の一部となる予冷凝縮器138等、冷凍サイクルの高圧側の機器が収容され、これらを繋ぐ冷媒配管139が複数出入りする。
圧縮機120は冷蔵庫本体101の上部への設置を考慮して低騒音、低振動化を図りやすい内部低圧型でかつ往復動型の圧縮機を適用している。また、冷凍サイクル内の冷媒としては、地球環境保全の観点から地球温暖化係数が小さい可燃性冷媒であるイソブタンを使用している。
発熱を伴なう高圧側の機器である圧縮機120、予冷凝縮器138の放熱促進を図るため、強制通風用の放熱ファン140が圧縮機120と予冷凝縮器138との中間位置即ち機械室136の幅方向の中間位置に配置されている。放熱ファン140を中間にして強制通風の上流側に予冷凝縮器138、下流側に圧縮機120を配置し、上流側と下流側を区画形成している。
また、機械室136は上方と背方とが開放されており、この開放面を覆う形で機械室カバー141を機械室の外郭137に係合させて取り付けている。機械室カバー141は、樹脂で形成され、機械室136内の外部との空気の流通口142を備えている。空気の流通口142は、機械室136の幅方向に強制対流作用が行われるように構成されている。
以上のように構成された冷蔵庫において、以下その動作について説明する。
まず、圧縮機120を断熱箱体102の天面後方の機械室136に載置して、機械室136内の主要部品である圧縮機120、予冷凝縮器138を放熱ファン140で強制放熱することで機械室136の容積を小型化し冷蔵室103の収納容積を減少させずに、従来主であった最下方の貯蔵室である冷凍室106、107の後方領域には配置せず、断熱箱体102の最下部の奥行き方向での収納スペースを増大することができる。
さらに、貯蔵室側に形成した冷却室130を野菜室105、第二の冷凍室107に跨らせ極力突出させないことで、さらに奥行き方向の収納スペースが増すとともに、冷却室130が位置する下部区画118を奥行き方向でほぼ同一の大きさにすることができる。
したがって、第一の冷凍室106、第二の冷凍室107の奥行き方向の収納スペースを飛躍的に増大することが可能となる。この収納スペースの増大による収納性の向上は第一の冷凍室106が回転式扉であっても享受できるものであるが、第一の冷凍室106を引き出し式扉111で構成することで、収納物をその収納容器(図示せず)とともに引き出せるようになり収納物の出し入れ性を大きく向上することができる。また、第一の冷凍室106と第二の冷凍室107のように冷凍温度帯の貯蔵室を分割することによる、収納物の形状や目的に応じた区分収納をし、収納物の整理整頓や見分けが簡単になるという利点も有する。
すなわち、従来の冷蔵庫では最下段の貯蔵室を左右に分割すると、奥行き方向に圧縮機120の配置による収納スペースが確保できないため、非常に容量感のない手狭な印象を与え、事実、収納物も限られた形のものしか収納できないものであったが、本実施の形態では使用者が見下ろして収納物を確認し、出し入れする下部区画118に奥行き方向の充分な収納スペースを形成させるとともに、最下段の貯蔵室を左右に分割してもその広々感を確保したまま目的に応じた区分収納することができる。
また、下部区画118の貯蔵室の奥面が平面状になるため、その手前に位置する野菜室105の収納容器124や、第二の冷凍室107の収納容器125をほぼ直方体状に形成できるので、収納物の収納効率も向上する。特に一般的な冷凍食品である箱物を多く収納する第二の冷凍室107においては非常に効果的である。
上述したような効果は、販売構成上の主力機種である奥行き60cm以上の冷蔵庫においても有効であるが、食器棚とほぼ面一に設置できる薄型タイプの奥行き45cmから50cm程度の冷蔵庫であれば、奥行き方向の容量感が出て非常に有効になる。
次に、第一の冷凍室106を冷蔵庫本体101の前方向で収納容器(図示せず)のほぼ全体を引き出せるよう構成する、例えば引き出し式扉111を前後方向に摺動させるための引き出し代の長い摺動部材123を引き出し式扉111に支持固定することによって、従来取り出しにくかった貯蔵室内の奥側でも収納物を簡単に出し入れできるという利点を有する。この摺動部材123を他の引き出し式扉、例えば製氷室104、野菜室105、第二の冷凍室107の引き出し式扉109、110、112に使用しても上記と同様の効果を得ることが可能となる。
また、第二の冷凍室107も引き出し式扉にし、最下段の左右領域を双方ともに引き出し扉で構成することで、例えば図5に示すように使用者が冷蔵庫本体101の手前に立った状態で、その場所から移動しなくとも左右の扉を開き、収納物を横方向から出し入れができるようになる。
また、第一の冷凍室106を前後方向に摺動させる摺動部材123を断熱箱体102の断熱壁に設置し、引き出し式扉111を摺動部材123と連結固定させることで、従来から主であった貯蔵室の左右壁で支持する構成ではなく、摺動部材123が貯蔵室の左側の上下のみで構成できるので、右側分の無効スペースを活用し、貯蔵室内の収納スペースを増大することができる。さらに、隣の貯蔵室である第二の冷凍室107は相対的に同じ温度帯であるので、必要に応じて仕切壁を設けることなく貯蔵室を構成できるので、さらなる収納スペースの拡大と見た目の広々感を持つことが可能となる。
なお、下部区画118の幅方向ラインは同じで製氷室104の高さを低くし、第一の冷凍室106の高さを高くすることで、使用者の必要量に応じた貯蔵室の収納容量にすることができ、特に第一の冷凍室106はアイスクリームや細長い冷凍食品を立てて収納することもできて非常に便利である。
次に、冷蔵室103に関しては、上部区画117に設けた冷蔵室103の前面開口を塞ぐ扉108を分割し扉108aを構成することで、冷蔵室103の扉108に設けた収納ポケット140への区分収納ができるとともに必要に応じた扉開閉による温度上昇の低減が図れ、省エネにも繋がる。また、分割した一方の扉を製氷室104や第一の冷凍室106と同じ幅で構成することによって、冷蔵庫本体の上下方向の全高で縦ラインが一直線で構成することができるので、高級感とデザイン性の向上が図れる。
また、分割した冷蔵室103の扉108aを引き出し式扉とし、その下方に位置する製氷室104及び第一の冷凍室106も引き出し式扉で構成すると縦ラインの統一感とともに、冷蔵庫本体101の全高で構成される引き出し式扉の統一感も得ることが可能となる。さらに、扉108aの摺動部材150を断熱箱体102の左側の断熱壁に支持固定し、前後に引き出せるようにすると、冷蔵室103が扉108aの区画と扉108の区画との間に仕切りが必要なしに広々感をもったままの貯蔵室構成ができるとともに、ペットボトル、ビン類等を扉108aの引き出しに、大物や皿等を扉108の回転式に、という形で区画収納が可能となる。
本実施の形態における貯蔵室の配置に関しては、使用者の目線の位置にあり収納容量の大きい冷蔵室103は回転扉108を備え、室内の全体が正面で見渡せて収納物の出し入れがしやすい。比較的低い位置にある野菜室105は使いやすい高さ位置で引出し扉110を設けているため、腰を屈めず立ち姿勢のままで収納容器124を手前に引き出して上から覗き込んでの出し入れができ、重い野菜(キャベツ、白菜、大根)なども持ち上げることなくスムーズに出し入れができる。独立に設けた製氷室104は引き出し式扉109を備えており、氷を収納容器の上面からすくい出す動作をするのに、腰をかがめず楽な姿勢で取り出しができると同時に、他室からの臭い移りを防止しキレイな氷を提供することができる。比較的幅の狭い第一の冷凍室106は、ペットボトルやアイススティック、食パンなどを収納し、比較的幅の大きい第二の冷凍室107との使い分け区分収納ができる。
このように、本実施の形態では下部区画118の収納スペースを大きく増大させているため、複数の貯蔵室に分割、特に上下左右に分割しても手狭な印象を与えずに構成できることが最大の利点であり、使用形態に応じた区分収納ができるとともに、必要に応じた扉のみの開閉が行われ、使用者の開閉の負担や扉開閉による温度上昇が低減され、省エネにも繋がる。
以上のように、本発明にかかる冷蔵庫は、圧縮機を天面後方に収納し、最下段を左右領域に区画した引き出し扉を備えた貯蔵室で構成することで、収納スペースの増大と出し入れし易さを両立することができ、さらに目的に応じた区分収納及び使用頻度に応じたレイアウト構成にすることが可能となるので、同様の引出し扉を構成する冷蔵庫にも適用できる。
101 冷蔵庫本体
102 断熱箱体
103 冷蔵室
104 製氷室
105 野菜室
106 第一の冷凍室
107 第二の冷凍室
116 仕切壁
117 上部区画
118 下部区画
120 圧縮機
123 摺動部材
102 断熱箱体
103 冷蔵室
104 製氷室
105 野菜室
106 第一の冷凍室
107 第二の冷凍室
116 仕切壁
117 上部区画
118 下部区画
120 圧縮機
123 摺動部材
Claims (8)
- 冷蔵庫本体を形成する断熱箱体と、複数の貯蔵室と、前記複数の貯蔵室のそれぞれに前面開口部を塞ぐ扉と、前記断熱箱体の天面後方に設置された圧縮機とを備え、前記複数の貯蔵室のうち、前記冷蔵庫本体の最下段に位置する貯蔵室は左右に区画して形成され、少なくともその一方を引き出し式扉で構成することを特徴とする冷蔵庫。
- 前記引き出し式扉は、前記最下段の貯蔵室の他方よりも幅方向で小さくした請求項1に記載の冷蔵庫。
- 前記引き出し式扉は、奥行き方向で略全体を引き出せる構成にした請求項1または2に記載の冷蔵庫。
- 前記引き出し式扉は、前記断熱箱体の側壁に摺動部を備え、前後方向へ摺動させるよう構成した請求項2または3に記載の冷蔵庫。
- 前記断熱箱体を断熱された仕切壁によって上部区画と、下部区画とに区画形成し、前記下部区画は前面開口を塞ぐ扉によって左右の領域に区画され、前記左右の領域のいずれか一方の領域をさらに前面開口を塞ぐ扉によって上下の領域に区画するとともに、前記上下の領域を引き出し式扉で構成した請求項1から4のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
- 前記上部区画を冷蔵温度帯の貯蔵室とし、前記下部区画の前記引き出し式扉を備えた貯蔵室を冷凍温度帯の貯蔵室とし、前記引き出し式扉の上領域を製氷室とした請求項5に記載の冷蔵庫。
- 前記他方の領域を上下の領域に区画するとともに、その前面開口を引き出し式扉で構成し、その上方を野菜室とし、下方を冷凍室で形成した請求項5または6に記載の冷蔵庫。
- 前記上部区画の貯蔵室は、前面開口を塞ぐ扉を有し、その扉は前記製氷室の幅の延直線で左右に分割された請求項6または7に記載の冷蔵庫。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2005345683AJP2007147224A (ja) | 2005-11-30 | 2005-11-30 | 冷蔵庫 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2005345683AJP2007147224A (ja) | 2005-11-30 | 2005-11-30 | 冷蔵庫 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2007147224Atrue JP2007147224A (ja) | 2007-06-14 |
Family
ID=38208822
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2005345683AWithdrawnJP2007147224A (ja) | 2005-11-30 | 2005-11-30 | 冷蔵庫 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2007147224A (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102401530A (zh)* | 2011-12-06 | 2012-04-04 | 合肥美的荣事达电冰箱有限公司 | 冰箱 |
| CN104197603A (zh)* | 2014-08-19 | 2014-12-10 | 海信(山东)冰箱有限公司 | 一种冰箱 |
| CN110387308A (zh)* | 2018-04-23 | 2019-10-29 | 博西华电器(江苏)有限公司 | 发酵装置 |
| CN116067071A (zh)* | 2023-02-24 | 2023-05-05 | 海信冰箱有限公司 | 冰箱 |
- 2005
- 2005-11-30JPJP2005345683Apatent/JP2007147224A/janot_activeWithdrawn
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102401530A (zh)* | 2011-12-06 | 2012-04-04 | 合肥美的荣事达电冰箱有限公司 | 冰箱 |
| CN104197603A (zh)* | 2014-08-19 | 2014-12-10 | 海信(山东)冰箱有限公司 | 一种冰箱 |
| CN104197603B (zh)* | 2014-08-19 | 2016-04-20 | 海信(山东)冰箱有限公司 | 一种冰箱 |
| CN110387308A (zh)* | 2018-04-23 | 2019-10-29 | 博西华电器(江苏)有限公司 | 发酵装置 |
| CN116067071A (zh)* | 2023-02-24 | 2023-05-05 | 海信冰箱有限公司 | 冰箱 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP2351977A2 (en) | Refrigerator and Ice-Making System Thereof | |
| US20090167130A1 (en) | A dual drawer bottom mount freezer and mullion | |
| US10605516B2 (en) | Refrigerator appliance | |
| JP2008106993A (ja) | 冷蔵庫 | |
| KR20130094042A (ko) | 슬라이드 인출형 도어를 구비한 냉장고 | |
| JP7190731B2 (ja) | 冷蔵庫 | |
| JP2007064597A (ja) | 冷蔵庫 | |
| JP3931586B2 (ja) | 冷蔵庫 | |
| KR100727670B1 (ko) | 수납장이 구비되는 냉장고 | |
| JP2007147224A (ja) | 冷蔵庫 | |
| JP2007071429A (ja) | 冷蔵庫 | |
| US20190360741A1 (en) | Refrigerator appliance with multiple zone flexible chamber in door | |
| KR200468207Y1 (ko) | 냉장고 | |
| JP2008138903A (ja) | 冷蔵庫 | |
| JP2007163066A (ja) | 冷蔵庫 | |
| JP4200334B2 (ja) | 冷蔵庫 | |
| JP2006250421A (ja) | 冷蔵庫 | |
| JP2003166781A (ja) | 冷蔵庫 | |
| JP2003166775A (ja) | 冷蔵庫 | |
| JP2016038145A (ja) | 冷蔵庫 | |
| KR20120001956A (ko) | 냉장고 | |
| JP2007064593A (ja) | 冷蔵庫 | |
| JP3904023B2 (ja) | 冷蔵庫 | |
| JP2007064553A (ja) | 冷蔵庫 | |
| KR20100007495A (ko) | 냉장고 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date:20081021 | |
| A761 | Written withdrawal of application | Free format text:JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A761 Effective date:20090313 |