サクサク読めて、
アプリ限定の機能も多数!
住宅ローンの固定金利は、長期金利の代表的な指標となっている10年ものの国債の利回りを参考に各銀行が決めています。 10年ものの国債の利回りは、7月に入って一時およそ17年ぶりに1.6%まで上昇するなど高止まりが続いていて、大手銀行は8月適用する固定金利を相次いで引き上げました。 このうち10年固定で最も優遇する場合の金利では、三菱UFJ銀行が0.07ポイント引き上げて年1.95%と2011年以来の高い水準に、みずほ銀行が0.2ポイント引き上げて年1.9%と2015年以来の高い水準に、三井住友信託銀行も年2.095%に引き上げて2012年以来の高い水準になりました。 また、三井住友銀行は年2.05%、りそな銀行は年2.345%にそれぞれ引き上げました。 一方、利用者が多い変動型の住宅ローン金利は、5行とも7月と同じ水準にします。 金利の上昇によって利払いの負担が増える一方、預金の利息や国債の

自宅を売却したあと賃料を支払って住み続ける、「リースバック」というサービスをめぐり、高齢者からトラブルの相談が相次いでいて、国民生活センターが注意を呼びかけています。 「リースバック」高齢者中心に関心高まるも住宅の「リースバック」は、自分が暮らすマンションや戸建てなどを不動産業者に売却して現金を受け取り、その後は毎月、売却先に賃料を支払って、同じ家に住み続けられるサービスです。 住み慣れた家に住み続けながら、まとまった資金が手に入ることや、固定資産税や修繕積立金などの支払いがなくなることなどから、老後の資金を確保したい高齢者などを中心に関心が集まっています。 一方、不動産業者も、住民が住み続けることを前提に売買するため、市場価格よりも安く物件を取得できる傾向があり、空室リスクもなく、毎月家賃を得られます。 住民が退去したあとは、リノベーションして売却したり、賃貸として運用できたりするメリ

首都圏のマンションの一室で、住民や管理会社従業員らが集まり、テーブル越しに向き合っていた。5月17日、土曜日の午後。大規模修繕のための委員会の会合だった。 開始から30分近く。住民の1人が出席者の1…
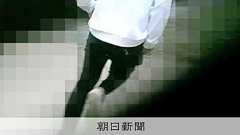
関東地方のマンションの老朽化などに伴う大規模修繕工事をめぐり、施工会社およそ20社が受注する会社や価格を事前の話し合いで決める違法な調整を繰り返していた疑いがあるとして、公正取引委員会が4日、一斉に立ち入り検査を行ったことが関係者への取材で分かりました。 立ち入り検査を受けたのは、いずれもマンションの修繕工事を行っている東京・港区の「長谷工リフォーム」や川崎市の「シンヨー」、それに東京・品川区の「中村塗装店」などおよそ20社です。 関係者によりますと、これらの社は、関東地方の複数のマンションの老朽化などに伴う大規模な修繕工事をめぐり、請け負う会社などを事前の話し合いで決める受注調整を繰り返し独占禁止法に違反した疑いがあるということです。 外壁の補修や防水工事などの大規模修繕工事は、マンションの所有者などで作る管理組合側が発注して複数の社の提案を比較検討する「見積もり合わせ」を行うケースが多

1年前の能登半島地震では住宅の倒壊が相次ぎ、特に高齢世帯の住宅耐震化の遅れが全国的な課題として指摘されました。こうした中、国土交通省は、耐震化の費用負担を軽減するため、リバースモーゲージと呼ばれる融資への新たな支援策を始めます。 リバースモーゲージは、住宅や土地を担保に融資を受け、生前は利子を支払い、亡くなったあとに売却して一括返済する制度で、将来、資産としては残せないものの、融資が受けやすくなる特徴があります。 高齢世帯の住宅耐震化の遅れが課題となる中、国土交通省は、住宅金融支援機構が手がけるリバースモーゲージを耐震化の費用を確保する手段にしようと、毎月の利子の支払いの負担を軽減する新たな支援策を始めます。 60歳以上は利子の支払いのうち3分の2を国が補助し、70歳以上は全額を国が補助します。 2025年度から順次、協力が得られた金融機関から受け付けを始めるということです。 国土交通省で

世界四季報 @4ki4 能登に3Dプリンター住宅 低価格、生活再建へ一助 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO… 2人世帯向け1LDK(トイレ、風呂付き)50平方メートルで550万円(税別)。高い鉄筋コンクリート造り。着工から平均約2週間で組み立てまで完了する。 pic.x.com/ZCAWACbC1I 2024-10-02 17:50:12 リンク 日本経済新聞 能登半島地震被災地に3Dプリンター住宅 低価格、生活再建へ一助 - 日本経済新聞 能登半島地震で甚大な被害を受けた石川県珠洲市で、3Dプリンターで造った住宅第1号が完成し、2日、報道陣に公開された。耐震性が高い鉄筋コンクリート造りで、料金も低価格に抑えられているのが特徴。能登地方は9月に豪雨にも見舞われ、多くの住宅が被害を受けた。製造を手がけた企業は、被災者の生活再建の一助としたい考えだ。住宅は、

能登半島地震で、石川県七尾市や津幡町など複数の地点で土を盛って造成した土地が崩壊し、住宅にも被害が出ていたことが専門家の調査で分かりました。

1日に発生した能登半島地震では木造住宅の倒壊が相次いだ。激しい揺れに襲われた石川県輪島市、珠洲市の街は壊滅的な状態で、いまだ被害の全容は明らかになっていない。これほどまでに甚大な被害をもたらした要因は何だったのか。 「まるで戦争の直後みたいだ。何もなくなってしまった」 能登半島の先端にある珠洲市で暮らす同市議の浜田隆伸さん(62)は、同市正院町の住宅街にある自宅周辺の惨状をそう説明し、落胆した。自宅は大きく損傷し、密集していた周囲の木造住宅は垂直方向に押しつぶされたように崩れ、残った瓦屋根が道路を塞いでいる。 年末年始で市内の実家に帰省していた女性(51)も驚きを隠せない。地震直後に慌てて家の外に出ると、近くの木造住宅が崩れ、瓦屋根がそのまま「ドスン」と大きな音を立てて地面に崩れ落ちた。「実家の周囲の住宅のうち7~8割は倒壊している」といい、複数の知人が家の下敷きになった。

震度6強の揺れを観測した、輪島市の中心部にある河井町では1日夕方、観光名所として知られる「朝市通り」周辺で火事があり消防によりますとこれまでにおよそ200棟が焼けたとみられるということです。 消防によりますと、地震による断水などで消火活動が影響が出たということです。警察と消防が、この火事で逃げ遅れたり、けがをしたりした人がいないか、確認を進めています。 午前6時50分ごろにNHKのヘリが撮影した映像では、観光名所として知られる「朝市通り」周辺で、複数の場所から炎が出て広い範囲で白い煙が上がり、火災が起きている様子が確認できます。周辺の建物は黒く焦げていて、建物が焼け落ちている場所もあります。 また7階建てとみられるビルが横向きに倒れている様子も確認できます。ビルの側面には「五島屋」という文字が見えます。 消防によりますと輪島市河井町にある輪島塗の老舗の会社のビルが倒壊したという情報があり、

マンションの修繕費などを賄うための積立金が不足するケースが増えています。修繕費の見積もりや徴収額の設定が不十分なことや、資材の高騰で修繕費が上昇していることなどが背景にあり、国土交通省は専門家による検討を始めました。マンションの修繕積立金など管理計画のガイドラインの見直しに向けて、国土交通省は30日、専門家による検討会で議論を始めました。 国の2018年度の調査では、修繕計画に対して積立金が不足しているマンションの割合は34.8%と5年間で2倍以上に増えているということです。 背景にあるのが、修繕費の見積もりや徴収額の設定が不十分なことです。 国土交通省によりますと、積立金の徴収額は築年数などに応じて段階的に引き上げていく方式が最近多く、新築マンションの修繕計画に関する調査では、最終的に見込まれる徴収額は初期の徴収額に比べ平均で3.6倍となり、中には10倍を超えるケースもあるということで

財務大臣の諮問機関、財政制度等審議会は、国として災害に強い街づくりを掲げる一方で、住宅の購入費用を支援する制度の中には、大雨などで浸水が想定される地域でも補助を認めているものがあるとして見直しを求めました。 財政制度等審議会は、19日の会合で街づくりや防災に関する予算のあり方について意見を交わしました。 この中で、財務省の担当者は、国土交通省などがさまざまな目的から設けている住宅の購入費用を支援する制度の中には、大雨などの浸水で大きな被害が想定される地域でも補助を認めているものがあると説明しました。 そのうえで、国として災害に強い街づくりを掲げる中、災害リスクの低い地域に住民を誘導するために補助の対象を絞ることなどが必要だと指摘し、委員からも、見直しを求める意見が挙がっていました。 財政制度等審議会の増田寛也会長代理は、審議会のあとの記者会見で「国としては災害リスクの低い地域に移り住んでも

単身の高齢者が賃貸住宅に入居しようとした際、孤立死のおそれを理由に断られるケースが少なくないことなどから、国はこうした住む場所の確保が難しい人たちへの支援について、ことし秋にも具体的な対策の方向性を示すことになりました。 一人暮らしの高齢者が賃貸住宅に入居しようとした際、孤立死が起きた場合に残される遺品の処分が難しいことを理由に、大家が入居を断るケースも少なくないことなどから、国は対策を話し合う検討会を設置することになりました。 検討会は国土交通省と厚生労働省、それに法務省が合同で設置し、3日、都内で開かれた初回の会議には、住宅や福祉の専門家などが出席しました。 会議では、多くの高齢者が賃貸住宅に住むようになっている一方で、住人が亡くなった後の遺品などの対応に困るケースが実際に出ていることや、住む場所を確保するための支援の担い手の確保などが課題になっていることが報告され、出席した委員からは

俺も、みんながまだ新築住宅主義でいてくれると助かる側の人間なんだけど、これからは賃貸派にとって追い風になるようなことも起きるかもしれないよ、と予測しています。 まず元増田が言うとおり、現時点でも、建材価格高騰と建設技能者の不足のダブルパンチによって、住宅取得価格がこの数年で1.2〜1.3倍ぐらいに上がっている。エビデンスとしては建設工事費デフレーターがある。 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_tk4_000112.html このデータの住宅総合の工事費を見ると、2015年7月を100とした指数値が、2018年3月期が102.8、2023年3月期には121.7と20%上がっていて、現場の感覚に近い(ちなみに現場感覚ではもっと上がっている)。これからもさらに上がるというのも元増田の指摘通り。5年前ぐらいの感覚で

●あとがき 相続で成り行き上賃貸マンションの大家になり10年が経った、約100部屋を自主管理している増田です。読んでくれた人ありがとうございました。なんかやっぱり議論がおかしな方向へ行っちゃうので消しますね。まあ、おかしな方向へ誘導しちゃったのは私だと思いますので、お前が言うな、ですが。 4本日記書いて沢山意見頂きました。一部「この人は不動産も金融もクッソわかってるな…」というハイレベルなコメントもあり、びっくりしました。 せっかく皆さんに話題にしてもらったので、個人的にはタトゥーが実際に入っている人や、そういう入居者を受け入れている大家に反論を書いて欲しいと思っていたのですが、この異様な雰囲気では難しく、いたずらにかき回して不安をあおってしまっただけかもしれませんね。申し訳ないです。 察しの通り私はめちゃくちゃ変わり者ですので、私みたいな極端な大家はまずいないと思います。この先の人生を賃

老朽化したマンションが増える中、国の法制審議会は建て替えの手続きなどを円滑に進めるため、いわゆる「マンション法」を見直す中間試案をまとめ、決議の要件の緩和などを盛り込みました。 築40年を超えるマンションは、20年後には全国で都市部を中心に、現在の4倍の425万戸に増える見込みで、老朽化への対応が課題になります。 このため、国の法制審議会の部会は、建て替えの手続きなどを円滑に進めるため「建物区分所有法」=いわゆる「マンション法」を見直す中間試案をまとめました。 試案では、それぞれの住居の所有者が不明になっている場合に備え、マンション建て替えの決議に現在、所有者の5分の4の賛成が必要だとしている規定について、4分の3の賛成に引き下げる案や、5分の4の賛成を維持し、耐震性が不足している場合は4分の3に引き下げる案などが示されました。 また、修繕などの決議については、現在の「保有者の過半数の賛成

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く