サクサク読めて、
アプリ限定の機能も多数!
デスクトップ用のモニターをはじめ、ノートパソコンのスクリーン、タブレット、スマホ、テレビ、プロジェクターなど、さまざまなデバイスのあらゆるスクリーンのドット抜け、単色テスト、グラデーションテスト、グリッドパターン、モーションテストができる無料ツールを紹介します。 今使っているデバイスの定期チェック、新しいデバイスを購入したとき、中古のデバイスを購入したときに、このツールを使って検証することができます。 Free Screen Test Tool Free Screen Test Toolはデスクトップのモニターからノートパソコン・タブレット・スマホまで、全デバイスのスクリーンのドット抜け・表示ムラをテストできる無料ツールです。 登録など面倒なことは一切不要、簡単に利用できます。 Free Screen Test Tool Free Screen Test Toolでテストできる機能は4つ。

はじめに こんにちは。Restaurant Service Devグループの高岡です。現在ぐるなびウエディングのフロントエンド開発・運用を行っています。 ぐるなびウエディングは結婚式場検索・予約サービスで、検索・会場詳細・特集・ランキングなど多様な機能を持つ大規模なウェブアプリケーションです。 そのぐるなびウエディングはリニューアルプロジェクトが進行しており、今年の7月に二次会検索と会場ページをリリースしました。 今回は大規模なウェブサービスのリニューアルにおいてチーム開発の効率性と保守性を両立するフロントエンドアーキテクチャをどう設計するか、ぐるなびウエディングリニューアルプロジェクトで実践した取り組みについて紹介します。 目次 はじめに 目次 開発体制 採用した技術スタック フレームワーク:Next.js App Router スタイリング:CSS Modules グローバルな状態管理

近年のスマートフォンはほとんどが何らかの急速充電規格に対応していますが、「急速充電はスマートフォンのバッテリーを消耗させる」といった説もささやかれています。ガジェット系YouTubeチャンネルのHTX Studioがこの説を検証するため、iPhoneとAndroidスマートフォンを使用して数カ月に及ぶテストを行った結果を報告しています。 Is Fast Charging Killing the Battery? A 2-Year Test on 40 Phones - YouTube Testing Whether Fast Charging Kills Smartphone Batteries, And Other Myths | Hackaday https://hackaday.com/2025/11/10/testing-whether-fast-charging-kills-sm

RHELのスペシャリストソリューションアーキテクトの田中司恩(@tnk4on)です。 2025年7月、Red Hatは、企業・組織内の開発者向けに、Red Hat Developer Programを介して「Red Hat EnterpriseLinux for Business Developers」という新たな無料サブスクリプションを発表しました。 developers.redhat.com Red Hat EnterpriseLinux (RHEL) は、安定性、信頼性、セキュリティを提供するエンタープライズLinuxプラットフォームとして世界をリードしています。開発者がこの強力なプラットフォームを無料で利用できるように、Red Hatは複数の無料サブスクリプションを提供していますが、特に個人の開発者か、組織内の開発者かによって選ぶべきものが異なります。 開発者向けのRHELサブ
こんにちは。株式会社EVERSTEELでソフトウェアエンジニアをしている日野原です。 主にフロントエンドを担当しており、技術としてはNext.jsを使用しています。(詳しい技術内容はこちらを参照) 少し前の話になりますが、ゼロからテストを導入したので、その過程や戦略について話していこうと思います。フロントエンドのテストを検討している方や、テストの運用方法を迷っている方の参考になるかと思います。Reactアプリにおけるテスト戦略と実践ガイド 一昔前はフロントエンド開発においてテストはあまり重要視されていませんでした。 しかし、フロントエンドの複雑さが増したため、最近ではテストが重要視されており、テストを書くことが求められています。 ただ、なぜテストが必要なのか、どのようなテストを書けば良いのか、どの程度のバランスでテストを構成すべきなのかは、十分に理解されていない場合も多いかと思います。

こんにちは、エンジニアの倉澤です。普段は「カミナシ教育」の開発に携わっています。 kaminashi.jp 今回は、10月に熱海で開催された開発合宿で Claude Codeの「サブエージェント」を教えてもらったので、それについて記事を書いてみました。AIエージェントを使いこなすためのヒントになれば幸いです。 ちなみにこのブログは開発合宿の最後の仕事として合宿中に執筆しています。 合宿についてはきっと誰かが詳細なブログを書いてくれると思うのでそちらをお待ちください。 去年の合宿の様子はこちら👉 エンジニア開発合宿2024を開催しました! - カミナシエンジニアブログ 1. 開発合宿のテーマとお題 今回の開発合宿は、「AIを上手に使いこなせるようになろう」的な目標が設定されていました。 お題としては、「AIエージェントのみを使って要件を満たすシステムを開発すること。人間は一切コードを

はじめに Codex は、多くの技術チーム(セキュリティ、プロダクトエンジニアリング、フロントエンド、API、インフラ、パフォーマンスエンジニアリングなど)で日常的に使用されています。 そして最近の Update では、AzureOpenAI のサポートにより、CLI または VS Code でも同等の Codex エクスペリエンスをご利用いただけるようになりました。 これを実現するために、以下の 5 つのプルリクエストをご提供しました。これにより、ChatGPT でお馴染みの Codex 機能をVSCode 上で安全に実行できるようになります。 個人的には、VSCode 上で Codex が使えるようになったことが一番嬉しいですね。VSCode ユーザーの方は是非一度お試しいただくと非常に感動する開発者体験が得られると思います。 見た目はこんな感じ。GitHub Copilot

はじめに こんにちは。CTO室 Platform開発チーム SREの原(@kouzyunJa)です。 ファインディでは日々サービスが爆速で開発されており、新しいプロダクトも次々と生まれています。それらのインフラ構築を、私たちのチームが支えています。 インフラ構築にもスピード感が求められるため、効率的かつ安全に進める仕組みが欠かせません。 今回は、そのスピード感あるインフラ構築を支えるTerraform Testの取り組みについてご紹介します。 はじめにTerraform Testの導入背景Terraform Testの書き方紹介 UnitテストとIntegrationテスト ディレクトリ構成 mock providorとUnitテスト 複数モジュールを組み合わせたIntegrationテスト CIワークフローでの活用 まとめTerraform Testの導入背景 developer.

こんにちは。ruby-devチームの遠藤(@mametter)です。 次期バージョンのRubyでは、pathnameがRuby本体組み込みとなり、require "pathname"なしで利用可能になる予定です。Rubyで書き捨てスクリプトを書いてる自分のような人は地味にうれしいかもしれません。 Feature #17473: Make Pathname toembedded class ofRuby -Ruby -Ruby Issue Tracking System さて、pathnameの組み込みがマージされた直後、非常に興味深いバグが発生しました。 今回はそのデバッグの経緯を技術ブログとして共有したいと思います。 問題の発生:特定環境でのみ失敗するテスト コミッタのhsbtさんがpathnameの組み込み化をマージした後、なぜかRubyのCIの一部が落ちるようになりました。
カミナシのソフトウェアエンジニアisanaです。 カミナシレポートの開発に携わっています。 私たちのチームでは、Webアプリケーションの品質担保のため、Playwrightを用いたブラウザテストを実装し、GitHub Actionsで実行しています。しかし、このCIプロセスにおいていくつかの課題がありました。 他方、ソフトウェア開発においては日々寄せられるVoCに対応したり、新機能の開発を行うなかで、負債や課題を上手くハンドリングしていく必要があります。本稿では、CIプロセスにおける課題をコスパよく解決するための改善策と、その過程で遭遇した「ハマったポイント」について、具体的な設定例を交えながらご紹介します。PlaywrightやGitHub Actionsを利用している開発者の方々にとって、少しでも参考になれば幸いです。 前提となる環境本稿で紹介する事例は、以下の環境を前提としてい

はじめに こんにちは。動詞です。 最近、Claude Codeを使った開発に重点を置いたPythonのプロジェクトテンプレートを作成しました。 しばらく運用しながら改善を重ねてきましたが、そろそろ使えるレベルになってきたので、覚書も兼ねてその設計について説明しようと思います。 Claude Code向けの設計 このテンプレートを作る上で意識したのは、Claude Codeが指示しなくても思い通りに動いてくれること、変な動きをしないことです。 そのために今回整備したものは、ざっくりと以下の2つに分けられます。 標準的な実装ルールの提示と支援ツールの導入 デバッグのループを回しやすい仕組み そして、これらをうまくClaude Codeに伝え、活用してくれるように、以下のような工夫をしました。 実装ルールを提示するだけではなく、モデルケースをリポジトリ内に配置し、適宜参照できるようにする 使って

「テスト文字列にうんこと入れるな」──ゲーム開発などを手掛けるインフィニットループ(札幌市)は5月13日、こんな呼びかけを行う新入社員向け研修資料の最新版を公開した。軽い気持ちで入れたテスト文字列が社外に漏えいした際のリスクについて説明した資料で、2021年に公開したものを、最新の事例などを交えたバージョンアップした。 資料は同社の松井健太郎代表取締役会長によるもの。テスト文字列で余計なユーモアを発揮すると、ミスによって外部に公開された際、トラブルの種になることを訴えている。そしてミスは必ず起こるため、“誤爆”があってもいいように無難を文字列を使おう──というのが資料の趣旨だ。 24年にもアップデートしていたが、25年版はさらに事例を追加した。国土交通省による証明書類のサンプルに、元ネタを知らないと対処できないネットミーム由来の文字列が紛れ込み、不適切な表現として対応に追い込まれた事態など

テストコードを実装する際に単体テストで書くか、統合テストで書くか迷う場面はないでしょうか。本エントリでは、私なりのテスト戦略についての考えをまとめました。 概要 対象アプリケーション本エントリにおける単体テストと統合テスト 単体テスト(ユニットテスト) 統合テスト(結合テスト、API テスト、フィーチャテスト) 単体テストと統合テストの特徴 テスト方針 テスト戦略 単体テストのみ 統合テストのみ 単体テストと統合テストを組み合わせる コンポーネント別のテストガイドライン 統合テストによるテスト テストピラミッドとテストダイヤモンド 統合テストの懸念 統合テストが無い 共有データセットが辛い 実行時間が遅くなりそう まとめ 参照 概要 単体テストと統合テストの特徴 テスト戦略 統合テストの懸念への対応NotebookLM による音声概要を作成しました。よくまとまっているのでこちらもどうぞ

カミナシで、Webフロントエンドエンジニアをしている osuzu です。 これまでフロントエンド専門外のエンジニアからReactを学ぶ良い方法やお勧めドキュメントを聞かれる度に、 公式ドキュメント のリンクを貼る日々を過ごしてきましたが、何かすごい上達方法がないものかと普段意識していることをこの記事で書き起こしてみました。 文字にした結果、中身になにか特別なことや魔法のテクニックは一つもなく、むしろプログラミング一般に通ずる話ばかりになりましたが、(自戒も込めて)凡事徹底することの難しさもあると感じておりその一助になれば幸いです。 ※ 凡事徹底:平凡なことを非凡なほどに実行すること。一つ一つの理解や実行は平易でも、それを実践し続けるのは難しい。React Server Component(以下RSC)を採用するかで変わる部分もありますが、記事の例はClient Componentの話が中

ほとんどのサービスとアプリケーションには、制限の大きなお試し版とも言える無料プランと、制限の緩和された有償プランがあります。さらに、有償プランのトライアルや、グループ開発向けのEnterpriseプランが用意されていることがあります。個々のサービスおよびアプリケーションについての料金体系の掲示は省くので、関心のあるものについてはまず無料プランから試すことをお勧めします。 アプリケーション構築は、多くの手順を必要とすることから比較的難易度の高い作業です。専用のウィザードがステップ・バイ・ステップで構築をフォローするスタイルは、今では「やりたいこと」を述べるだけでAIが代行してくれるようになりました。デザインも、直接アプリケーション構築に持ち込むことができます。 スタイリッシュなUIを生成するv0 ▲v0 v0(ブイゼロ)は、Next.jsの開発元であるVercel Labsによる、AIを活用
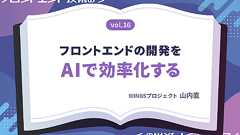
Devin.aiを試す 長くなってきたので切り出した Devin.aiを試す2024 2025-01-02SessionUsage Limitについて Devin went to sleep due tosessionusage limits. Limitをだいぶ超えてから止まるようだw 追記 説明を読むとセッション単位のように読めますが、最後のユーザーの発言以降で使用できる ACUs の上限 (by teramoto) あ、そうなんだ、どうりで超えてるものもあるなぁと思った Devin観察日記 3日目|Daiki Teramoto nishio 「さて、いよいよ金銭感覚が麻痺して参りました。一歩先の未来を生きるためのコストとして受け入れつつも、たまに冷静になる瞬間が恐ろしいです。」 あーあー聞こえないーー(1ヶ月のトークンを1週間で使い切っておかわりした人) nishio 冗談は
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く