サクサク読めて、
アプリ限定の機能も多数!
村山悟郎Goro Murayama @goromurayama 美大で教えていると、現代の芸術表現の在り方が難しい局面にあることを感じざるをえない。端的に言うと、極めて私的なモチーフからしか表現を出発できない学生が増えている。 (以下、ツリーで書きます) 2025-12-03 11:30:51 村山悟郎Goro Murayama @goromurayama 芸術は、科学のように普遍一般の真理を探究するのではなく、個別具体と普遍一般の複合領域に存在する。だから必ずしも私的なモチーフから出発するのが悪いわけではないが、そのモチーフを接続しうる普遍一般の美術理論・批評・社会状況がもはや見定められず(細分化と分断)、 2025-12-03 11:31:41 村山悟郎Goro Murayama @goromurayama 強いてあげればメディア環境(インターネット・SNS・AI)くらいである。
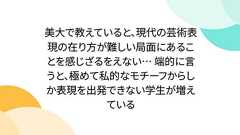
松岡美桜🌸🍼 @Matsuoka_miou 小腹すいたからおにぎりまとめて頼もうと思ってUberしたんだけどさ この書き方と写真的に何個かわかれて来ると思うじゃん。 そしたらこんなの来てビックリしてる( i꒳i ) ちゃんと美味しく頂きます。笑 pic.x.com/5GtcjEaIXd 2025-12-01 04:52:07

Cloudflare services are currently operating normally. We are no longerobserving elevatederrors or latency across thenetwork. Our engineering teams continue to closely monitor the platform and perform a deeper investigation into theearlier disruption, but no configuration changes are being made at this time. At this point,it is considered safe to re-enable anyCloudflare services that were tem
関連記事 Adobeの大規模障害、依然復旧せず 被害範囲は“Macのみ”か 「ネットを切ってアプリを再起動して」 11月18日朝から続く、Adobe製品の大規模障害。公式からの復旧報告は同日午後6時時点では確認できず、依然障害が続いている。 「中国外交部ジェネレーター」話題 ツールが同時多発、SNSは大喜利に 台湾現地メディアも反応 高市早苗総理が11月7日の衆議院予算委員会で「台湾有事は存立危機事態になり得る」と発言し、それを撤回しないことを受け、中国外交部は13日から15日にかけてXで「台湾問題で火遊びをするな」などと警告する画像を複数公開した。一方、中国外交部の投稿を模した画像ジェネレーターが同時多発的に生まれ、日本で話題になっている。AWS、19日からの大規模障害について謝罪し、再発防止策を発表AWSは、19日からの大規模障害について謝罪と概要を公開した。障害の引き金となったD

「19のいのち」のサイトURLをクリックすると、「お探しのページは見つかりませんでした」と表示された(NHKのサイトより)NHKの新しい配信サービス「NHK ONE」がスタートした裏で、これまでNHKが独自に調査、報道してきた記事や動画を集めたサイトが相次いで消滅している。 【あの問題の後も…】「NHKは遅れている」 いずれも多くの記者やディレクターなどが時間と費用をかけて制作した優良コンテンツばかりで、特定のサイトを挙げて「消さないで」と求める署名活動も始まっている。 これらのサイト、なぜ閉鎖されたのか。そして、復活することはないのか。NHKに問い合わせた。NHKは10月1日、新たにインターネット配信サービス「NHK ONE」を開始した。当初、システムの不具合が発生し、登録するための手続きがわかりにくいといった声が多く上がった。 そんな中、NHKがこれまで労力をかけて作り上げた特設サ

すいません、釣りタイトルに見せかけて釣りじゃないガチなやつです。 最近よく見かけるALT属性の誤った使い方 最近、X(旧Twitter)などのSNSで、画像につける「ALT」という機能を、本来とは違う目的で使ってる人をちょくちょく見かける。 例えば: ポストできる文字数に収まらないから続きを書く 検索に引っかからないように、隠しメッセージを書く 「見たい人だけ読んでね」っていう、ちょっとした裏話を書く 画像と全然関係ない愚痴や感想を書き連ねる(いわゆるお気持ち表明。同時に反論対策) よくわからないセンシティブポエムを書く こういう使い方、見たことある人も多いんじゃないですかね。見たことない人は幸運です。 一見すると「ちょっとした工夫」に見えるし、考えついた人には誰も困らないように思えたのかもしれないですね。 でも実は、この使い方は非常に大きな問題を引き起こします。 実際に以下に引用する一連
(報道発表資料) 2025年8月1日NTT東日本株式会社 「フレッツ・VPN アドバンス」の提供開始についてNTT東日本株式会社(以下NTT東日本)は、新たなVPNサービスである「フレッツ・VPN アドバンス」(以下、本サービス)を2026年2月より提供します。本サービスでは、最大概ね10Gbpsの高速アクセス回線※1に標準対応し、閉域でのセキュアなVPNサービスとインターネット接続をワンストップ提供することを実現しました。 ※1最大概ね10Gbpsの高速回線をご利用いただくには、フレッツ 光クロス、およびフレッツ 光クロス Biz回線のご契約が必要です。技術規格上の最大値であり、実効速度ではありません。 1.提供の背景と目的 昨今、急速なAIの普及やクラウド利用の拡大などによる通信需要の高まりにより、安全かつ高速で安定した閉域網内での拠点間通信に加え、企業のIT情報システム管理者

済み @yamapikarya5インターネット老人会 ↑ しかし誰も“古”のネットをリアルタイムで体験しておらず、ゼロ年代後半〜10年代生まれのガキが2chやおもしろFlash倉庫のネタを擦ってネット古参のふりをしながら馴れ合っている 2025-07-28 20:41:47

昔俺は自作ホームページを持っていた。 今の若い人にはもう伝わらず、インターネット老人は耳を塞ぐアレだ。Yahooか何かが提供していたテンプレートを使ったインスタントなページで、細々日記の更新や掲示板での交流を楽しんでいた。 しかし高校受験に入ると時間がなかったり興味が他に移ったりして、ある時俺はホームページを削除することに決めた。 元々大して熱量のないホームページである。高校に受かった俺はホームページのことなんてすっかり忘れて日々を過ごしていた。 一年後、俺16歳。パソコンのメールボックスに見慣れないアドレスからのメールが入っていた。 「貴殿ホームページの書き込みについて」 今と違ってインターネットは非常に閉じた空間だったこともあり、最初に思ったことは「え? 俺がホームページ持ってたことをなんで知ってるん?」だったように思う。 メールの本文は剣呑そのものだった。さすがに一言一句覚えちゃい

マー@MANIMANI @maaasenyooo 洋ゲーと創作が好きなまむちうです。 4コマなど描くインターネットおえかきまむ。サキュバスのメロメロとかを描いています。TFに強めの幻覚を見ているので注意。 onlymaaa.jimdofree.com

「エンジニアの背中を預かる」をミッションに掲げるGMO FlattSecurity 代表取締役CEOの井手です。 2025年7月8日より、GMOインターネットグループと提携して「GMOオープンソース開発者応援プログラム」をリリースいたしました。GMOとして「すべての人に安心な未来を」というキャッチフレーズのもと行っている「ネットのセキュリティもGMO」プロジェクトの第四弾として、弊社のプロダクトである「Takumi byGMO(以下、Takumi)」をOSS開発者の皆様に無料で提供させていただくことができる運びとなりました。 「Takumi」の提供によりOSS(オープンソースソフトウェア)のセキュリティ対策における脆弱性検出から修正までの工数を大幅に削減するほか、従来発見が困難だった潜在的な脆弱性を網羅的に検出することで、より迅速な修正対応を可能にし、これまで以上にインターネットの安全に

>参政が伸びるのはどうすればよかったんだ! ほんの2カ月前まで国民が伸びてたんだからそのままでよかったのに、手取り増をほったらかして不倫と反ワクを公認して、党首が不倫したせいだろ。 手取りを増やす、現役層を見据えた政策重視の政党がでれば普通に伸びるよ— 神奈いです (@kana_ides) July 6, 2025 今回、「参政党が伸びる」というのを”客観的な事実”として予想したメディアとか、政治評論家がどれぐらいで、いつから発言したかをちょっと調べてみたい。それは飯の種、実績だから気づけば語ってた筈。…たぶん、皆言わなかった。兆候は本当に無かった、直近の伸長ではないかhttps://t.co/EOJT1C6qzp— Gryphon(INVISIBLE暫定的再起動 m-dojo) (@gryphonjapan) 2025年7月6日 俺基準ではほんの少し反響が多いけど、これはまだ仮説というか

気がついたら2024年どころか2025年も半分過ぎていた。 というわけで、直近1年分をまとめて紹介する。 今回は5冊に絞り込んだ。 2024年下半期から2025年上半期に読んで面白かった本 1. NEXUS 情報の人類史 2. ヴィクトリア朝時代のインターネット 3. 傷つきやすいアメリカの大学生たち 大学と若者をダメにする「善意」と「誤った信念」の正体 4. 男はなぜ孤独死するのか 5. 「怠惰」なんて存在しない 終わりなき生産性競争から抜け出すための幸福論 終わりに2023年下半期から2024年上半期に読んで面白かった本 2024年下半期から2025年上半期に読んで面白かった本 気がつけばまた1年が経っていたので、急いで書かなければと思いながら必死に書き上げた。さて、なぜ今年はこんなことになっているのか。理由は分かりきっている。AIのせいだ。AIを触るのが楽しくて、かなりの時間を取ら

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く