 工学部化学システム工学科の実験風景
工学部化学システム工学科の実験風景

工学部化学システム工学科の実験風景
Your Dream × Niigata University
新潟大学の未来を開くメッセージを発信
150年の歴史を有し、九つの学部と七つの研究科が集う新潟大学は、日本海側で随一の規模を誇る総合大学だ。世界でもトップレベルの脳研究所を擁するなど、研究力にも定評がある。教育理念は「自律と創生」だ。そこから一歩先を行く新しい時代の人材育成を目指し、ステートメント(宣言)を策定した(下)。さらに、これからの新潟大学を象徴する言葉として選ばれたのが「真の強さを学ぶ。」だ。これらの力強いメッセージとともに、教育の質をより一層高めることに力を注ぐ。
その一つが、現在申請中の創生学部(仮称)の新設だ。同時に理、工、農の理系学部で複数に分かれていた学科をまとめ、1学科体制になる計画も進んでいる。こうした構想にはどのような思いが込められているのか。髙橋姿(すがた)学長に聞いた。
「社会ではものごとを解決する能力が問われます。それには多角的なものの見方が必要です。理系学部は一つの学科にすることで、異なる分野を幅広く学びます。創生学部では自分で考え行動する、新たな価値を創造できる人材を育成します。その点において新学部のコンセプトには自信があり、新しい教育のあり方だと思っています」
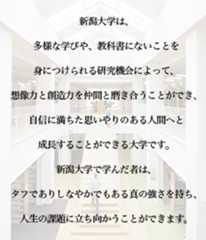
幅広い領域を横断する多様な学び
そもそも新潟大学は、主専攻プログラムと副専攻プログラムという2通りの履修体系がある。主専攻は所属する学部が提示するプログラム。副専攻は主専攻で学ぶ領域以外の分野の授業を履修するもので、「法律学」「環境学」など21のプログラムが用意されている。所属する学部の学位を取れるのはもちろん、副専攻で学んだことについても認定証が授与される。主と副、いわば縦糸と横糸が織りなすように深い専門知識と幅広い教養を身につけることができる。
多様な学びはそれだけではない。新潟大学にはダブルホームという独自の制度がある。すべての学生が地域と連携して取り組んでいるプロジェクトに参加することができるというものだ。過疎・高齢化の進む村落で稲作の手伝いをしたり、地域活性化のためのイベントを住民と実行したり、活動の内容は多岐にわたる。異なる学部学科の同級生、先輩、地域の人々とつながることで、学部学科とは違ったもう一つの「ホーム」をつくることができる。
「学生たちは年上の大人と接することで、社会人としてのコミュニケーションの方法を体得します。ある意味、これもインターンシップです」
三本の柱を軸に多彩な人材の育成を

「地域活性化にも力を注ぎたい」と語る髙橋姿学長
地域に根ざす一方、髙橋学長は「どんどん外に出て、力を試してほしい」と話す。日本海に面する新潟市は港町として発展した、グローバルな気質が備わる土地だ。新潟大学も中国やロシアなどの大学と交流が深く、毎年、多くの学生が行き来している。近年は東南アジアや中東からの留学生も増えている。
「本学は新潟の立地を生かし、環東アジア地域の教育研究拠点の形成を目指しています。そのために大学間協定を増やしていく予定です。教育、研究、社会貢献。この三本の柱を軸に、地域から国際社会に至るまで、あらゆるフィールドで活躍できるタフでしなやかな人材育成に努めます」
大学発研究所
脳研究のトップランナー 認知症の解明に全力投球

左から柿田明美教授、池内健教授、五十嵐博中教授
ヒトの脳は21世紀最後のフロンティアといわれる。この謎に満ちた人体最大の機能に迫るのが新潟大学脳研究所(以下、脳研)だ。1967年に日本で初めて国立大学付属の脳研究の場として誕生して以来、日本のヒト脳研究を牽引(けんいん)する。
近年、大きな期待を寄せられているのが、認知症の予防、診断、治療法の確立だ。脳研では、分野の違う研究者たちが、認知症の全容解明に向けて尽力する。
池内健教授率いる生命科学リソース研究センターでは、バイオマーカーの実用化を目指す。これは、血液や脳脊髄(のうせきずい)液に含まれる微量分子や遺伝子などを解析し、未症状の段階から認知症を予見しようというもの。五十嵐博中教授率いる統合脳機能研究センターでは、最先端の磁気共鳴装置で脳内の画像を写し取り、早期診断に役立てる研究を行っている。脳を傷つけないので患者の負担も軽減される。そして、柿田明美教授率いる病理学チームは、認知症患者の脳細胞を解析し、ファイナルアンサーを導き出す。病理解剖なくして、認知症の本当の姿は見えてこない。検体された脳はできるだけ早く適切な形で標本にする。脳研は凍結標本だけでも3万点を超える試料を保存し、質・量ともに世界でも屈指のブレインバンクだ。「これは患者様とご家族の協力があってこそ。付属病院の臨床2科と連携し、チームワークで研究に臨む。これが脳研の最大の強みです」(柿田教授)
3人の研究者に共通するのは研究に対する熱意と根気。病気に苦しむ人を救いたいという思いがそれを支える。
自分で目標を設定し、課題解決の力を養う社会のニーズに応える新学部「創生学部(仮称)」を構想


2017年4月の新設を計画している創生学部(仮称)は、学生一人ひとりが自分で目標と課題を設定し、専門領域を学んでいくという新しい形の教育プログラムだ。学生は初年次から科学技術、文化、環境、福祉などさまざまな分野の問題を把握する授業を受け、自分は何を目標に何を学ぶべきかを徹底的に考える。そして自らの課題を見つけ、それに応じた科目を選択する。総合大学の強みを生かし、人文、法、経済、理、工、農の各学部から22の専門領域に関する科目パッケージが提供される予定なので、専門は幅広い分野から選択が可能だ。
ほかにも地域・産業界での学修を行う「フィールドスタディーズ」、専門分野の知識を総合的に活用し、チームで課題解決を実践する「ソリューションラボ」など、特色のある授業科目がそろう。これらを通して、自分で学ぶ力はもちろん、魅力的なアイデアを具体的なプランに仕上げる企画力や、仲間と協力しながら目標を達成させるためのコミュニケーション力が身につく。さらに実践的な英語に関する授業や、データの活用に関する授業なども用意されており、卒業後のキャリア形成を踏まえながら多様なスキルを得ることができる。
実際、県内外の336の企業、官公庁にアンケートを実施したところ、下のグラフのような結果が出た。創生学部で養われる「自分で考え行動し、課題を解決する力」は、いま社会で求められているのだ。


※336の企業・官公庁へのアンケート結果から(進研アド提供)
「さまざまな企業の方から期待の声をいただきました。深い専門知識と幅広い教養を備え、新しいことに果敢にチャレンジする。創生学部ではそんな『創造型』の人材を育てたいと思っています」(髙橋姿学長)
※2017年4月設置申請中のため、内容は変更となる場合があります。
朝日新聞デジタルに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
Copyright © The Asahi Shimbun Company. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.



























