書架とラフレンツェ
読書記録メモです。ネタバレがバリバリです。
この広告は、90日以上更新していないブログに表示しています。
高速で論文がバリバリ読める落合先生のフォーマットがいい感じだったのでメモ
(図書館学系の話題でもあるからちょっと悩んだけれど、文献読解全般に関する内容だからこちらへ)
既に日々論文をバリバリ読んでいるひとには今更な記事だろうけれど、分野ごとの違いもあって興味深かったのでざっくり記録する。
論文を大量に読む際に、頭から几帳面に読んでいると時間がどれほどあっても足りないし、後から「こんなことが書いてあった論文なんだったっけ?」という問題も発生してしまう。
研究者の皆様はMendeley などの文献管理ツールをを用いていることが多いかとは思うが、それでも論文の読み方そのものに工夫をすればインプット/アウトプットの効率が圧倒的によくなるので、やってみるにこしたことはない。
その工夫とは何かというと、論文を読むときに「特定の問いに集中して読む」というものだ。学術論文は分野ごとの違いはあれ、必ず特定の流れに従って構成されている。そこで要点のみに注目して読み、他の事項を捨てることで高速かつ要点を踏まえた論文の読み込みができるのだ。
以下に紹介するものは落合陽一先生が「先端技術とメディア表現1 #FTMA15」 のスライド65枚目で紹介していた論文まとめのフォーマットだ。実験論文用だが、以下のような構成になっている。
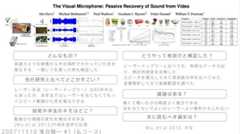
- どんなもの?
- 先行研究と比べてどこがすごい?
- 技術や手法のキモはどこ?
- どうやって有効だと検証した?
- 議論はある?
- 次に読むべき論文は?
このフォーマットに従って問いを埋めていくだけで、論文ひとつの内容をA4半分~1枚に圧縮できる。これで出来上がるものはその論文の「オレオレ要旨」ともいえるものだ。
論文にはほぼ必ず要旨がついているものだけれど、論文によって要旨の記載事項はバラバラだから要旨をそのままインデックスには使えない。また、普段なじみのない作法で書かれた他分野の論文を読む時には、自分ならではのフォーマットに従って読んだ方がより素早く理解でき利用すべきポイントも簡単に見いだせる。
こうしたフォーマットは実験論文に適用するもの以外にも考えられる。例えば、理論研究だったら下記のようなものがあり得る。
- どんなもの?
- 批判されている理論は何?
- どういう文脈・理路をたどっている?
- 対象となるスコープにおいて網羅性と整合性はある?
- 議論はある?
- 次に読むべき論文は?
このフォーマットに従うと、オレオレ要旨だけではなく自動的に文献批判の骨子までできてしまう。
また「集めた文献をどう整理すべきか?→知のフロント(前線)を浮かび上がらせるレビュー・マトリクスという方法 読書猿Classic: between / beyond readers」では、レビュー・マトリクスというフォーマットを用いての文献整理を紹介している。こちらは医療・疫学分野で役立ちそうなフォーマットで、各論文を横断的に比較できる強力なものだ。このフォーマットの出典はこちらの本。
これらの読解用フォーマットは、論文を書く際のフォーマットとは必ずしも一致しない。著者にとって重要な文脈や要点が、読者にとってもそうだとは限らないからだ。
個別のテーマに従って文献を収集している場合、特にこうしたフォーマットが威力を発揮する。ある特定のテーマの文献研究用に特別なフォーマットを作成するのもよい。著者が想定した論文の読み方にはならないかもしれないが、論文は娯楽小説ではなくて問題解決のために読まれるものだ。著者の考えた論の流れに乗っかったままでいると、「結局、自分のテーマにとってこの論文はどういう意義があったのか?」を見失ってしまうこともある。明白な文脈を断ち書いていないことを見出すような妄想力を発揮さえしなければ、論文の読み方は各人の自由で構わない。
この世に「論文の書き方」と銘打った、書く側の視点に立った論文構成法はたくさん紹介されている。しかし論文の読み方という観点ではそれほど独立した資料がないようだ。この点、書誌学的にも興味深いところなので、また追って調べてみたい。
それと、もし皆さんが「自分はこんなの使ってる!」というのがあればぜひ教えてください。


