サクサク読めて、
アプリ限定の機能も多数!
今回で、記事の数がちょうど百になりました(一覧は除く)。 元々「読書感想文」は、ホームページにおいて日記の一部として、ごくたまに書いていたものです。ある程度形式を決めて、定期的に更新するようになったのは、ブログに移行した二〇一一年五月以降のことでした。 取り上げるのは新刊でも話題の本でもないので、時流から外れ、のんびりしたペースで楽しんで書くことができました。尤も、そのせいで、たった百の記事を書くのに何年もかかってしまいましたが……。 僕にとって読書遍歴を晒すのは、それなりに勇気のいることです。読書好きであれば、どんな本を読んでいるかで、センスや好み、その人との相性が凡そ分かってしまうからです。いわば過去の恋人の特徴をこと細かく描写するようなもので、悪趣味の誹りを受ける可能性もあるでしょう。 とはいえ、僕の記事が、誰かの快適な読書の助けにならないとも限りません。 そう前向きに考え、しばらく
外国の書籍などを著作権者の許諾がなくても点字や音声データとして相互利用できるようにした国際条約が、モロッコで28日まで開かれた国連機関「世界知的所有権機関(WIPO)」(本部・ジュネーブ)の外交会議で採択された。従来は許諾手続きが煩雑なだけでなく、海外の出版社や著者に著作権料を求められるケースもあった。条約発効後は視覚障害者が海外の作品を楽しむ機会が広がるとみられる。 関係者によると、同会議で27日(現地時間)に日本を含む加盟185カ国の全会一致で採択された。各国が条約を批准、発効すれば、早ければ数年以内に視覚障害者向けの読書環境が改善する。 日本の著作権法では、日本国内で公表されている著作物については、点字に翻訳(点訳)する場合、営利・非営利を問わずに活用を認めている。音声データも点字図書館が制作する場合だけは、例外的に著作者の許諾なしで音声翻訳を認めている。 しかし、米国など海外に流通
古書店街として知られる東京・千代田区神田神保町に28日、SFや音楽など専門分野を持つ全国の40店舗が出店した古書店モールがオープンした。 運営会社の社長、河野真さん(57)は「読みたい人が、読みたい本に出会える場所になれば」と話している。 この店は「スーパー源氏神保町店」。河野さんは約360の古書店が加盟する古書のネット通販サイトを運営しており、今回、実際の店舗として開店した。 河野さんによると、古書についてもインターネット上で様々な情報が簡単に入手できるようになっており、近年、古書店数は減少傾向にあるという。ただ、専門分野を持つ店の人気は根強く、希少な本を分野別にそろえた専門店を開くことで、本好きのニーズに応えることにした。 店内には絶版本も含め、国内外のSF、ミステリー小説や音楽、演劇、精神世界など、出店した各店が得意とする分野の古書のほか、作家・井上ひさしさんの草稿など、直筆の原稿用
国立青少年教育振興機構が全国の中高生を対象に行った調査で、半数以上の中高生が、読書好きと答える一方、1か月間で学校や地域の図書館から全く本を借りていない生徒が7割以上に上ることが分かった。 同機構が昨年3月、全国から抽出した中高生約2万1000人を対象に調査した。この結果、読書が「とても好き」「わりと好き」と答えた中学生は67%、高校生は59・7%だった。「この1か月で本を読みましたか」との問いには、中学生82%、高校生56・2%が「読んだ」と答えた。 学校図書館で1か月あたり何冊の本を借りるかについては、「0冊」と回答した生徒が、高校生82%、中学生72・4%に上った。地域図書館でも「0冊」としたのは、高校生85・2%、中学生78・3%だった。
朝日新聞2011年1月30日読書面に掲載された鼎談を再録します。 ◇ 筒井康隆さんが読書面で連載した『漂流――本から本へ』が朝日新聞出版から本になりました。筒井さんと、同学年の大江健三郎さん、このほど本をめぐる随筆集『星のあひびき』が出た丸谷才一さん。3人の作家による「読書について」の鼎談(ていだん)では、豊かで多彩な読書体験が語られました。(構成・大上朝美) ■面白い本を飛び石伝いに 筒井 大江 僕は『漂流』推薦の言葉に「面白ヒトスジの大読書家」と書きました。筒井さんは子どもの時から面白い本をつかまえる名人で、つかまえたら正面から熱中する。自分に根を下ろすよう大切にする。その後、一つ一つが書かれるものの柱になります。最初は俳優になりたかったのが、ある時から小説家の自分を自覚する。その方向に読み進む過程が、あざやかなドラマですね。 丸谷 読書に対するエネルギーに圧倒されるね。僕なんかとても

Author:くるぶし(読書猿)twitter:@kurubushi_rm カテゴリ別記事一覧 新しい本が出ました。読書猿『ゼロからの読書教室』NHK出版 2025/5/23刊行読書猿『独学大全』ダイヤモンド社 2020/9/29書籍版刊行、電子書籍10/21配信。 ISBN-13 : 978-4478108536 2021/06/02 11刷決定 累計200,000部(紙+電子)2022/10/26 14刷決定 累計260,000部(紙+電子) 紀伊國屋じんぶん大賞2021 第3位 アンダー29.5人文書大賞2021 新刊部門 第1位 第2の著作です。 2017/11/20刊行、4刷まで来ました。読書猿 (著) 『問題解決大全』 ISBN:978-4894517806 2017/12/18 電書出ました。Kindle版・楽天Kobo版・iBooks版韓国語版 『문제해결 대

理数系ネタ、パソコン、フランス語の話が中心。 量子テレポーテーションや超弦理論の理解を目指して勉強を続けています! 先日、このブログの理数系書籍の紹介記事が200冊に達した。4分の3ほどが大学、大学院の教科書レベルの物理学書や数学書、残りがブルーバックスに代表されるような一般向けの本だ。 記事で紹介した物理学と数学の本は「書名一覧」でご覧いただけるほか、ブログの「記事一覧(分野別)」にまとめてある。また、最近読み始めた電子工学系の本の記事は「電子工学」のカテゴリーで検索できる。 物理や数学の教科書や専門書を読んだことがない人は次のように思っているかもしれないから、この膨大な読書体験で何が得られたか、僕がどう感じたかなど感想を書いておくのもいいかもしれない。 - これだけたくさんの本を読むと、どのようなことがどれくらいの深さで理解できるようになるのか? - いろいろな疑問が解決することで、自

出版状況クロニクル55(2012年11月1日〜11月30日) 出版社・取次・書店という近代出版流通システムがスタートしたのは明治20年代、すなわち1890年前後であり、その歴史はすでに120年余に及んでいることになる。しかもそれが未曾有の危機に追いやられていることは周知の事実だといっていい。さらにまたその出版危機が日本だけで起きている特異な現象だということも。 日本の近代出版業界の流れは教科書、雑誌、書籍、戦後はコミックが加わり、形成されたと見なせるだろう。それらのインフラの中心は出版業界の三者ではあったとしても、とりわけ書籍に関しては、大正期の1910年代から古書業界が、流通販売だけでなく、生産に関しても大きな役割を果たし、リバリュー、リサイクルも含め、出版業界のバックヤードとして機能してきた。 それらの中でも赤本、特価本業界は出版に関して独特の位置を占め、貸本、大衆小説、コミックの揺籃
たった1人で出版社を営む。元フリーター、36歳。自らが惚(ほ)れこんだ、埋もれた作品の復刊が主だ。夏葉社の島田潤一郎さんは、営業だって自分の足で全国を飛び回る。吉祥寺(武蔵野市)で起業して丸3年。一歩ずつ、そしてしっかりと愛好家の心をつかんでいる。 島田さんが読書にのめり込んだのは、大学生のころ。卒業後は小説家を志し、アルバイトを転々としたほどだ。ただ、一読者として、新刊は洪水のように出版されるのに、読み継ぐべき本がどんどん絶版になっていく現状を憂えていた。 32歳のときに職を探すも、50社受けて全滅。親友だったいとこが急死したことも重なり、何かが吹っ切れた。「自分でいい本をつくって、多くの人に届ければいい」。自らの貯金をもとに2009年9月、夏葉社を立ち上げた。 出版や編集の経験はもちろんゼロ。吉祥寺を選んだのは、書店が多く、よく遊びにきていた街だったから。駅前に借りた6畳のワンルームマ
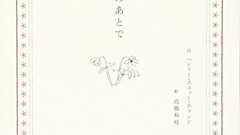
毎日新聞が全国学校図書館協議会(全国SLA)と合同で実施した「第58回学校読書調査」の結果が26日まとまった。中学生と高校生に一番好きな作家を聞いたところ、1位はともにホラー作家の山田悠介で、他を圧倒した。 全国の公立学校に通う小中高校生を対象に6月に実施、1万1313人の回答を得た。 あらかじめ選んだ30人から一番好きな作家を答えてもらうと、中学生は18%、高校生は22%が山田悠介を挙げた。2位は中学生があさのあつこ(8%)、高校生が東野圭吾(12%)だった。 山田悠介は、若者を主人公に猟奇殺人や自殺などを奇抜な発想で描く作家。01年に自費出版した「リアル鬼ごっこ」が49万部のベストセラーになり、10作品以上が映画やドラマ、舞台化されている。女子にファンが多く、中学女子は21%(男子14%)、高校女子は24%(男子21%)が一番好きと答えた。 一方、中学生の27%、高校生の19%は好きな
雑ネタ,本 NAVER まとめで話題になっていた下記の記事。本に年100万使う私が選ぶ!値段の10倍得する本10選 - NAVER まとめ年間で100万円を書籍代にぶち込むというまとめ主が、その豊富な読書体験の中から精選した珠玉の10冊を紹介するというものなのだが、少し高めに見積もっても1冊2,000円前後の自己啓発書が中心のようなので、おそらく500冊程度の自己啓発書を読んだ上でのラインナップなのだと思われる。読んだことのない本も含まれているのでそのセレクトに対しての論評や感想は控えるが、「大変だなあ」とは思った。 で、ここから先は上記記事には全く関係なくなるのだが、ある日、口元に豊かな髭を蓄えた、シルクハットを頭に載せた細身の老人が俺の目の前に現れて「この100万をあなたにさし上げましょう。ただし、本を買う以外には使ってはいけませんよ、それではごきげんよう」と、インクのいい匂いのする
推理小説の皮を被った衒学迷宮。 中世の修道院の連続殺人事件の話という入口から、知の宝庫(だけど大迷宮)へ誘われる、これぞスゴ本。 二十年前と一緒だった、知恵熱で寝込んだ。というのも、ただ物語を追うだけでなく、自分の既読を強制して引き出させられる体験が強烈だったから。 「読む」というのは目の前の一冊に対する単独の行為ではない。台詞や描写やモチーフ通じて、関連する本や自分の記憶を掘り出しては照射しながら、くんずほぐれつ再構成する、一種の格闘なのだ。ひっくり返すと、あらゆる本にはネタ元がある。「読む」とは、ネタ元を探しては裏切られながら、『再発見』する行為なのだ。 ヨハネの黙示録の引用に始まり、ヴィトゲンシュタインの論理哲学考の模倣で終わる本書は、縦横無尽の借用、置換、暗示、物真似で綴られており、科学・文学・哲学の壮大なパッチワークを見ているようだ。 だいたい、探偵役が「バスカヴィルのウィリアム

毎日の定期的な読書を再開しようと習慣づける努力をしている。 そういう時に「読書にまつわる本」を読むとモチベーションがあがるケースがある。 僕の場合だと、斉藤孝の「読書力」やアドラーの「本を読む本」が昔そうであった。 最近の本よりなるべく古典的なものがよかったので、今回は加藤周一の「読書術」を読む。 タイトル通りテクニックについて書かれている本ではあるが、 その調子が読書の「方法」ずばりを俗に言う「どや顔」で解説するというよりか、 エッセイ風味であり文章のリズムや「漢字とひらがな、カタカナのバランス」が非常に良く読みやすい。 さくっと1時間ほどで半速読してしまった。 速読術や精読術にも触れているのだが、 ふっと肩の力が抜けるところが『本を読まない「読書術」』という章で印象に残った。 要約すると世の中全ての本、ましては地方の図書館にある蔵書レベルでも全てのものを読むことは不可能であり、 何を読
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く