サクサク読めて、
アプリ限定の機能も多数!
不浄の血 アイザック・バシェヴィス・シンガー傑作選 著者:アイザック・バシェヴィス・シンガー 出版社:河出書房新社 ジャンル:小説・文学 不浄の血 [著]アイザック・バシェヴィス・シンガー アイザック・B・シンガーは1978年に米国人作家としてノーベル文学賞を受賞した。英語作家としてではなく、多くの地に散るユダヤ人の共同体が守り伝えてきたイディッシュ語作家として。 短編を1、2本、私も大学生の頃に読んだ記憶がある。だが当時私はアイザック・B・シンガーの持つ言語的な事情をうまく想像出来なかった。だから、少し風変わりな話だったという印象しかない。 ところが、今回出版された『不浄の血』は風変わりどころではない。民話と呪いと旧約聖書の言葉と多くの魔物たちと超人と村人が入り交じった異物としての文学である。 著者はポーランドから米国に移住し、イディッシュ語で書き、それが英語に訳されて流布するうち、自ら

1945年3月の神戸大空襲は米軍の無差別空爆ではなく、住宅密集地を徹底攻撃し、住民を標的にしたものだったとの調査結果を、日本の空襲史を研究している中山伊佐男さん(83)=東京都在住=がまとめた。中山さんは「米軍は狙いを定めず都市を爆撃したと言われているが、実は緻密に計画し、住民を徹底的に標的にしていた。無差別という言葉を使うと空襲の本質を見失ってしまう」と指摘している。 神戸大空襲は3月17日未明にB29爆撃機309機が来襲。兵庫区や長田区など神戸市西部を中心に焼夷(しょうい)弾を投下した。約2700人が亡くなり、6万9000戸が被災した。 中山さんは米軍が1943年秋ごろに作成した「焼夷攻撃データ」に着目した。データは、日本側が作った地図や写真のほか、火災保険額の査定資料といった空襲目標施設の詳細な資料まで加味されていた。米軍はこれを基に、住宅の密集度が40%を超える地区を高密度居住
「日本国語大辞典」、通称「日国(にっこく)」という辞書がある。 この辞書は全14巻、その規模・充実度は他の追随を許さない。 といっても、全14巻・220,500円だけの空間と金銭を用意するのは簡単ではない(特に前者)。 せめて 1巻だけでもと購入した人もいて、記事を読むとその陶酔具合が伝わってくるが、ぼくにはなかなかそれすらもできず、ジャパンナレッジに年会費 15,750円(ちょうど日国 1巻分だ)を納めてネットで使っている*1。 ただ、その人のこの言葉はいただけない。 この大著の中に載録されていない日本語は、すなわち日本語ではないということなのだよ、君。 http://d.hatena.ne.jp/the-world-is-yours/20110530/p2 いや、どんなに優れた辞書であっても、それは言葉を映す「鏡」にすぎない。 鏡と実態に違いがあったら、間違っているのは常に鏡で、実態の
七月十七日夜、記者会見場にて今までに見たことのない数のカメラを前にした際、不思議なことに心がスッと軽くなった。 もっと緊張しろよサクラギ、テレビカメラは何でも映すぞ、お前の虚栄心も自己顕示欲も嘘(うそ)も。今まで蓋をしてきた何もかもをさらす時が来たんだ。自覚はあるのか。 体の内側では最高音で警笛が鳴っているのに、だ。会場に向かって頭を下げた瞬間、手足の震えは止まり、田舎のおばちゃんは「桜木紫乃」になった。 「何もかもを映すのなら、映してくれ。どう隠しても文章に人間が出てしまうように、カメラだってどう撮っても人を映してしまう。ならば我々は同志だ。仲良くしようじゃないか」 さぁ腹をくくれ。北海道人は総じて面倒くさがりが多いのだ。結婚式は会費制だし、香典にも領収書が出る土地。そんなところで生まれ育った人間が、内地に根を張る日本の文化に上手(うま)く絡んで行けるわけもないのだから。 初代開拓民だっ
先日BLOGOS上で「奨学金」という名の学生ローン 1,000万円超す借金抱える若者も、という記事が話題になりました。奨学金を利用している学生や、返済に困っている社会人が「教育の機会均等」を訴えてデモを起こしたというものです。 まずは奨学金を「学生ローン」に 記事内の写真の見出しに 「日本の奨学金は借金だ」。制度の本質をついたプラカードが目についた。 というものがありまして、本質というか、もう当たり前の話だよね。という感じです。当然ネットでの反応も、「奨学金は借金に決まってんじゃねーか、お前が自分で借りたんだろ。借りたもんは返すのがあたりめーだろ!アホ!」となっています。 デモをしている人たちのフォーカスはそこではないのでしょうが、やはりそのあたりの内部と外部の意識の差を取っ払うには、まず奨学金の名称を変更する必要があると思います。アメリカでは学生に貸し付けるお金のことは「学生ローン」と呼

忘れられない日本人移民 ブラジルへ渡った記録映像作家の旅 著者:岡村 淳 出版社:港の人 ジャンル:エッセイ・自伝・ノンフィクション 忘れられない日本人移民―ブラジルへ渡った記録映像作家の旅 [著]岡村淳 著者の岡村淳は1987年にブラジルに移住して以来、小型ビデオカメラを片手にたった一人でドキュメンタリーを撮り続けている。彼の初期の代表作が、ナメクジの生態を記録した番組であることの意味は大きい。 カタツムリが平気でも、ある意味〈家なし〉のカタツムリであるナメクジを嫌悪する人は多い。「無視され、あるいは偏見を浴びせられている存在」に視線を傾けずにはいられないところにこの希有(けう)な記録映像作家の特質がある。 日本からブラジルに渡った移民は二つの国の言語・文化の〈あいだ〉を生きざるをえない、いわば〈家〉なき存在である。労苦を重ね、ひどい差別を受けながらも、たくましく生き抜いてきた名もなき日
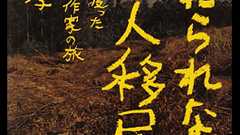
◇私(わたし)たち日本人(にっぽんじん)は、あのとんでもない爆弾(ばくだん)の正体(しょうたい)を世界(せかい)に伝(つた)えていく使命(しめい)があります 2010年(ねん)に75歳(さい)で亡(な)くなった小説家(しょうせつか)で劇作家(げきさっか)の井上(いのうえ)ひさしさんは、一貫(いっかん)して反戦(はんせん)、平和(へいわ)を訴(うった)え続(つづ)けました。とくに、戦争(せんそう)を放棄(ほうき)することを定(さだ)めた日本国憲法(にっぽんこくけんぽう)への思(おも)いは強(つよ)いものでした。【篠口純子(しのぐちじゅんこ)】 ◇10歳(さい)で終戦(しゅうせん)、養護施設(ようごしせつ)で育(そだ)つ 5歳(さい)で父(ちち)を亡(な)くし、10歳(さい)で終戦(しゅうせん)を迎(むか)えました。中学(ちゅうがく)、高校時代(こうこうじだい)は児童養護施設(じどうようごしせ
◇戦争(せんそう)はやってはいけない。戦争(せんそう)は人間(にんげん)を抹殺(まっさつ)しますから、いかなる理由(りゆう)があっても絶対(ぜったい)にやってはいけません。 8月(がつ)は67年前(ねんまえ)、日本(にっぽん)が戦争(せんそう)に負(ま)けた月(つき)です。戦争(せんそう)を体験(たいけん)し、生(い)き残(のこ)った人(ひと)たちは、残念(ざんねん)ながらどんどん亡(な)くなっています。最近亡(さいきんな)くなった著名人(ちょめいじん)の、平和(へいわ)への思(おも)いを伝(つた)えます。第(だい)1回(かい)は5月(がつ)29日(にち)に100歳(さい)で死去(しきょ)した脚本家(きゃくほんか)・映画監督(えいがかんとく)の新藤兼人(しんどうかねと)さんです。 ◇「一枚(いちまい)のハガキ」受賞会見(じゅしょうかいけん)で 「戦争(せんそう)はやってはいけない。戦争(せ
死にゆくひとが手のひらにのせてくれたパン切れは、ひからび、かびていた。 マグダ・オランデール=ラフォンさんは、ハンガリーに生まれた。十六歳のとき、アウシュビッツ=ビルケナウに強制収容され、家族のなかでただひとり、生還した。収容されたひとびとは、毎日二列にわけられる。ガス室か、労働か。母と妹は、到着した日に殺された。 どうしてこんなことになってしまったのか。 ユダヤ人というだけで、大量虐殺を犯した母国。ささいなけんかをした家族に、あやまれなかった。そして、ひとり生き残った。 ベルギーをへてフランスに渡った彼女は、母語を失うほど、記憶を封じた。生きのびるために生きつづけ、夫と子どもを得ることで、愛とほほえみをとりもどす。そして、三十年の沈黙ののち、はじめての光を放つ。 あらわれた言葉は、静かでまぶしい。経験したおぞましい闇をはねとばし、歴史をおそれるひとびとを、自己内省の入口へと導く。 声もか
小型国語辞典では売り上げ1位の『新明解国語辞典』(三省堂)の第7版が刊行された。「新明解」は個性的な解釈で多くの「愛読者」を持つ。その代表として、『新解さんの読み方』の著者に思いを寄せてもらった。2位の『岩波国語辞典』(岩波書店)の新しい版も11月に出た。合わせて魅力を探った。 ◇ 新解さんの本名は、新明解国語辞典(三省堂刊)といって、日本で一番売れている国語辞典です。今月一日に第七版が出たので、わたしは朝から晩まで、電車の中でも昼休みでも新解さんを引いている。どこがどう変わり、何が残ったのか調べないと気が済まない。 「新解さんの魅力は何ですか?」と訊(き)かれたら、「それは、自分で引いてみると誰でも宝探しの楽しさを味わえることです」と、大きな声で答えたい。新解さんの宝は、語釈、用例、運用欄、序、歴史的かなづかいの文章に埋めてあるので、とにかく引けばすぐわかる。「読書」「恋愛」「性交」の語

広告やブックデザインなど、広いジャンルで活躍する人気アートディレクターが、絵と言葉が伝えるものは何か、「わかりやすさ」とは何かを興味深く語っている。 絵で情報を伝えることは情報をそのまま絵にすることではない。「リンゴ」という言葉をただリンゴの絵にしても、文字で書くのと変わらない。一口かじられたリンゴにすると人の気配が現れる。そのそばに女性が倒れていると、怪しげな空気が生じる。自分の仕事は絵と言葉が作り出す、この奇妙な空気や響きを扱うことだという。 しかし、絵があれば物事はわかりやすいかといえば、それはちがうとも述べている。そもそも「わかる」とはどういうことか。私たちがうまく説明できない、ぼやっとした部分を、著者は仕事でぶつかったさまざまなできごとや身近な例えに置き換えながら、ごくシンプルな言葉で核心をぽんと取り出してみせる。そのたびにあっと目の前が開けるような、爽快な衝撃が訪れる。 後半に
![コラム別に読む : 絵と言葉の一研究 [著]寄藤文平 - 谷本束 | BOOK.asahi.com:朝日新聞社の書評サイト](/image.pl?url=https%3a%2f%2fcdn-ak-scissors.b.st-hatena.com%2fimage%2fsquare%2f09fc3651d195e7f70a63bdaa59c89460e3bbd04c%2fheight%3d288%3bversion%3d1%3bwidth%3d512%2fhttps%253A%252F%252Fimages-fe.ssl-images-amazon.com%252Fimages%252FI%252F51a-GV0OpoL.jpg&f=jpg&w=240)
社説[中村文子さん死去]沖縄戦継承に力尽くす Tweet 2013年6月28日 10時00分(24時間25分前に更新) 沖縄戦記録フィルム1フィート運動の会事務局長を長く務めた中村文子さんが亡くなった。99歳だった。自らを「軍国教師」と呼び、その贖罪(しょくざい)から戦場へ送った教え子を思い続け、平和運動に身をささげた半生だった。 晩年は会の顧問として運動の一線から退いていた。しかし、運動を共にしたメンバーには、二度と沖縄を戦場にしないよう戦争の悲惨さを語り継ぐ活動を続けるよう伝えていたという。 〈語り継ぎ語り継ぐべしあの悲惨 知らざる子らにまたその子らに〉 中村さんが自著に残した短歌に、あらためて沖縄戦を語り継ぐ強い意志を感じる。心からご冥福をお祈りし、先達の平和への思いを引き継ぐ決意を新たにしたい。 中村さんの思いは、1フィートの会を立ち上げた初代代表でひめゆり学徒引率教師の仲宗根政善
ぼくらの文章教室 作者: 高橋源一郎出版社/メーカー: 朝日新聞出版発売日: 2013/04/05メディア: 単行本この商品を含むブログ (5件) を見る 内容紹介 どうすれば上手な文章を書けるようになるのだろうか。 そのためにはまず、自分の好きな文章たちを見つけること。 そしてその文章たちの中に入りこみ、 「びっくりしたり、感動したり、うろたえたりしているうちに、 ……『文章』の成分のようなものがしみついて」くると、 タカハシさんはいう。 たとえば、タカハシさんが好きなのは、明治から昭和にかけて生きた貧しい農婦である木村セン。 彼女は遺書を残そうとして文字の手習いをはじめた。 障子紙の切れっ端に色鉛筆で書かれたその文章は短く、 ことばにも文字にも誤りがあるのに、なぜか力強く響く。 これは「名文」以上の文章ではないか。 あるいは、免疫学者の故多田富雄さんの『残夢整理』の文章。 これは作者が

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く